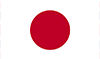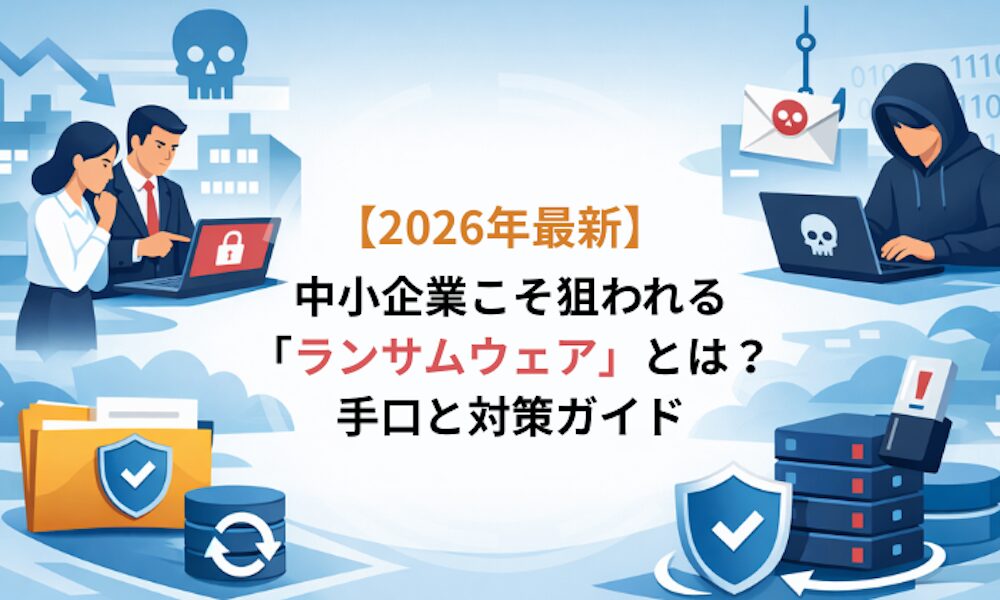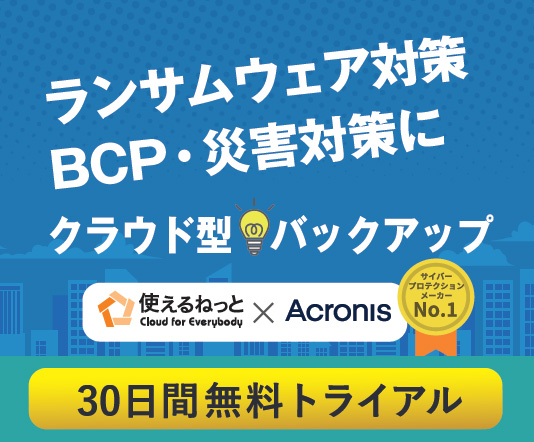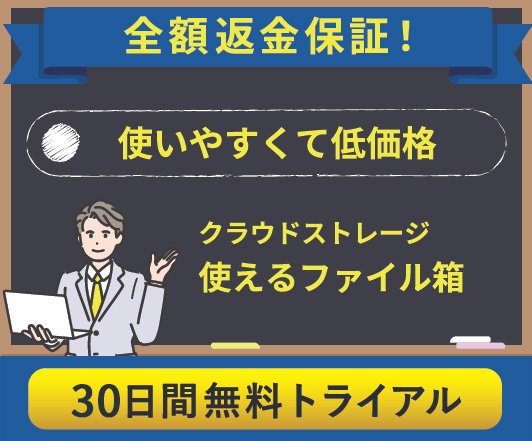ビジネスの現場では今なおメールが主要なコミュニケーション手段であり続けています。しかしその一方で、サイバー攻撃の入口として狙われやすいのもメールです。巧妙なスパムメール、標的型攻撃、情報漏えいといった脅威は年々多様化しており、早急な対策が求められています。
本記事では、企業が導入すべきメールセキュリティソフトの選び方、必須機能、比較基準を専門的かつわかりやすく解説します。自社のニーズに合った最適な製品を選ぶための知識を得ることができます。
目次
なぜ今、メールセキュリティソフトが不可欠なのか?増大する脅威とリスク
メールセキュリティソフトの主な種類と特徴
失敗しない!メールセキュリティソフト選びの重要ポイントと比較基準
【2025年版】おすすめメールセキュリティソフト比較表(法人向け)
特定の課題を解決するメールセキュリティ機能例
メールセキュリティソフト導入後の運用と注意点
使えるねっとが提供するメールセキュリティソリューションのご紹介
まとめ
なぜ今、メールセキュリティソフトが不可欠なのか?増大する脅威とリスク

国内外で相次ぐ被害事例
中小企業を含め、すべての企業はメールによるセキュリティインシデントが決して「対岸の火事」ではないことを認識すべきです。
実際、近年では、Emotetなどのマルウェアが再び猛威を振るい、国内の大学や自治体、医療機関などでも被害が相次ぎました。これらの多くはメールを介した感染であり、「メール=安全」という過信が危機を招いています。
2025年現在、Emotetの活動は沈静化しています。しかし、特定企業を狙った「標的型攻撃メール」など、メール関連のセキュリティインシデントがおさまる気配はありません。
例えば、2024年2月には製造業を狙った標的型攻撃メールが複数の企業で報告されました。メールには「納期確認」と記載され、エクセルファイルが添付されており、取引先を巧妙に装ったものでした。しかし、この添付ファイルにランサムウェアが仕込まれており、この攻撃により数千万円規模の損害が発生した企業もありました。
主要なメール脅威とその被害
ここでは、主要なメール脅威の種類を6つ挙げ、その被害例や企業への影響についてまとめます。
| 脅威の種類 | 概要 | 主な被害例 | 企業への影響 |
スパムメール(迷惑メール) | 大量に送信される広告や詐欺目的の不要メール | ・業務用アカウントへの大量受信 ・偽サイトへの誘導 | ・業務効率の低下 ・従業員の注意力散漫 ・マルウェア感染の入口となることも |
標的型攻撃メール(BEC・スピアフィッシング) | 経営者や取引先になりすまし、特定の個人を狙って送信される詐欺メール | ・経理担当者を騙して送金させる(BEC) ・役員名義の偽メールで情報を取得(スピアフィッシング) | ・金銭的被害 ・取引先との信用失墜 ・法的・社会的な責任問題 |
| ランサムウェア | 添付ファイルやリンク経由で感染し、データを暗号化して身代金を要求するマルウェア | ・社内ファイルやシステムの暗号化 ・復旧のために数百万円以上の支払い要求 | ・業務停止による損害 ・取引の遅延・停止 ・多額の復旧コスト |
| ウイルス・マルウェア | メール添付やリンクから侵入し、システムを破壊・情報を盗み出すプログラム | ・不正アクセスの足掛かりとなる ・顧客情報の抜き取りや転送 | ・機密情報の漏えい ・法令違反や社会的信用の低下 ・サーバダウンなどの障害 |
| 誤送信による情報漏えい | 宛先ミスや添付ファイルの間違いにより、意図しない相手に情報が届く | ・BCC漏れによる顧客情報の流出 ・関係者外への資料送信 | ・個人情報保護法違反のリスク ・顧客・取引先からの信頼失墜 ・社内統制の見直しコスト |
| PPAP問題 | ZIPファイルとパスワードを別送する運用がセキュリティリスクになる | ・ZIPファイルが改ざんされても気付きにくい ・攻撃者によるパスワードの傍受 | ・安全性が低く、受信側での開封拒否も増加 ・業務フローの見直しが必要に |
メールセキュリティソフトの主な種類と特徴

ここでは、上述のメールを介した脅威から自社の情報資産を守るために、メールセキュリティソフトの提供形態や仕組み、それぞれのメリットとデメリットについて見てみましょう。
| 提供形態・種別 | 仕組み・特徴 | 主なメリット | 主なデメリット | 向いている企業・ケース |
| クラウド型(SaaS) | インターネット上で提供されるサービスを利用。DNS設定変更によってメールがSaaS側を経由し、ウイルス・スパムを除去したうえで社内に転送される。 | ・インフラ不要で即日導入可能 ・常に最新の脅威定義・フィルタリングが適用される ・外出先・テレワークでも同じ保護が受けられる ・スケーラビリティが高く、利用者数に応じて柔軟対応可能 | ・カスタマイズ性に限界あり(ログ保存期間・動作ポリシーなど) ・インターネット環境が前提 ・機密性の高い業界では外部経由が懸念されることも | ・中小企業、スタートアップ、ITリソースが限られている企業 ・初期コストを抑えて迅速に導入したい場合 |
| ゲートウェイ型(アプライアンス/ソフトウェア) | 社内ネットワークのメールサーバ前段に設置。メールトラフィックを一括監視し、ウイルス、スパム、標的型攻撃などを検知・ブロック。ハードウェアまたは仮想アプライアンスとして提供される。 | ・高度な制御が可能(細かいポリシー設定やログ分析) ・内部ネットワーク全体をカバーできる ・外部メールサーバと連携しやすい | ・導入・設定に専門知識が必要 ・初期導入費用が高額になりやすい ・ネットワーク構成変更が必要な場合がある | ・情報システム部門が整備されている中~大企業 ・メールのセキュリティポリシーを細かく管理したい企業 |
| エンドポイント型(クライアントソフト) | 各端末(PCやノートPC)に専用のセキュリティソフトをインストール。メールソフトと連携して、受信・送信時にスキャンを実施。 | ・テレワーク・モバイル環境での利用に最適 ・利用者ごとのアクティビティを細かく制御可能 ・他のエンドポイント対策(DLP、USB制御など)と統合しやすい | ・台数が多いと運用負荷が急増 ・利用者が設定を無効にするリスクあり ・セキュリティ水準が端末ごとにばらつく可能性 | ・モバイルワーク・ハイブリッドワークを採用している企業 ・個々の端末で柔軟な制御を行いたい企業 |
| オンプレミス型 | 自社サーバ上にソフトウェアをインストールして構築。メールサーバと連携し、自社のネットワーク内だけでセキュリティ対策を完結させる。 | ・完全自社運用でデータ漏えいリスクを最小化 ・高度なカスタマイズが可能(ログ保持、UI、通知ルールなど) ・長期的にはランニングコストを抑えられる可能性 | ・導入・構築コストが高く、時間も必要 ・最新の脅威に対して手動でアップデートが必要 ・セキュリティインシデント時の即時対応体制が必要 | ・金融・官公庁・医療など高い機密性が求められる業界 ・自社セキュリティポリシーが厳格で、外部依存を避けたい組織 |
失敗しない!メールセキュリティソフト選びの重要ポイントと比較基準

メールセキュリティソフトの導入は、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクから企業を守るうえで極めて重要です。しかし、数ある製品の中から自社に最適なものを選ぶには、目的や環境に応じたチェックポイントを明確にし、冷静に比較検討する必要があります。
以下では、選定時に押さえるべき7つの観点と、その具体的な比較基準を紹介します。
1. 対応できる脅威と必要な機能の洗い出し
まずは「自社がどのような脅威にさらされているか」を把握することが第一歩です。たとえば以下のような脅威に対して、必要な機能を整理しましょう。
| 脅威 | 必要な機能 |
| スパム(迷惑メール) | アンチスパム、ブラックリスト/ホワイトリスト |
| 標的型攻撃(BEC・スピア型攻撃) | URLフィルタリング、サンドボックス検査 |
| ウイルス・マルウェア | 添付ファイル無害化、リアルタイムスキャン |
| 誤送信による情報漏えい | 送信メールの保留、上長承認、DLP(情報漏えい防止) |
| なりすましメール | SPF/DKIM/DMARC対応 |
ポイント:
・どの機能が必須か、優先順位をつけておくと選定時に迷いません。
・自社のインシデント履歴やセキュリティリスク分析と連動させて検討すると効果的です。
2. 提供形態と自社の環境・運用体制との適合性
ソフトの導入形態は「クラウド型」か「オンプレミス型」かによって運用負荷や柔軟性が大きく異なります。
| 項目 | 検討ポイント |
| クラウド型 | IT担当者が少ない企業でも導入・運用しやすい。スピード導入・スケーラビリティに優れる。 |
| オンプレミス型 | カスタマイズ性が高く、自社ネットワーク内で運用可能。情報漏えいリスクを懸念する企業に適する。 |
| 運用負荷 | 更新やメンテナンスの自動化可否、トラブル時の対応手順を事前確認する。 |
| グループウェアとの連携 | Microsoft 365、Google Workspaceとの連携の深さ(添付制限・自動検査・メールログとの連動など)を確認。 |
ポイント:
・自社のITリソース(IT担当者の有無)に応じて、導入形態を選ぶことが重要です。
・ハイブリッドワークを導入している場合は、クラウド型の柔軟性が活きます。
3. 価格・料金体系の妥当性
価格は「月額費用が安いかどうか」だけでなく、総コストと機能のバランスで考える必要があります。
| 比較軸 | チェックポイント例 |
| 初期費用 | 導入ライセンス費・設定費用が必要か、無料トライアル後の本契約が必要か |
| 月額・年額費用 | ユーザー単位・ドメイン単位・メール数単位などの課金方式を確認 |
| オプション料金 | サンドボックス、DLP、誤送信防止機能などが標準かオプションか |
| 費用対効果 | 1件のインシデントによる損害額(数十万円〜数千万円)と比較し、ROIを試算 |
ポイント:
・安さだけで判断せず、「どこまで守れるか」で投資対効果(ROI)を考える視点が重要です。
4. サポート体制の充実度
いざという時に頼れるサポート体制が整っているかも重要な評価基準です。
| チェック項目 | 確認すべき内容 |
| 日本語サポート | マニュアル・問い合わせ対応が完全日本語か |
| 対応時間 | 平日のみ、もしくは24時間365日対応か |
| 問い合わせ方法 | 電話・チャット・メールなど、即時対応が可能な手段があるか |
| 導入支援 | 初期設定や移行支援、教育コンテンツの有無を確認 |
ポイント:
・海外製品では、国内代理店による充実したサポートがあるか要確認です。
5. 使いやすさと管理のしやすさ
導入後に「使いにくくて放置される」とならないよう、UI/UXのチェックは必須です。
| 項目 | チェックポイント例 |
| 管理画面の操作性 | ポリシー設定やアラートの確認が直感的にできるか |
| レポート機能 | 日次・週次レポート、誤検知率・脅威傾向などが自動生成されるか |
| トライアルの有無 | 無料で一定期間試せるか(操作性・検出力・レポート内容を体験) |
ポイント:
・情報システム担当だけでなく、非専門の担当者でも扱える操作性が理想です。
6. 導入実績と信頼性
導入実績や第三者認証の有無は、製品の信頼性を判断する有効な指標です。
| 項目 | チェックポイント |
| 導入企業数 | 数百社以上の導入があるか、特に自社と同業種での実績があるか |
| 導入事例 | 実名での事例紹介・ユーザーインタビューが公式サイト等に掲載されているか |
| 第三者認証 | ISO/IEC 27001、SOC 2、ISMSクラウド認証などのセキュリティ認証の有無 |
ポイント:
・セキュリティ製品は「実績が信頼の証」です。ベンダーの継続性(倒産リスクなど)も考慮しましょう。
7. 「脱PPAP」への対応
PPAP(パスワード付きZIP+別メール送信)はセキュリティ上のリスクが高く、脱PPAP対応は必須です。
| 対応機能 | 検討ポイント |
| ファイルの自動アップロード | 添付ファイルを自動でクラウドストレージに保存し、リンクを共有する機能の有無 |
| パスワードレス共有 | ワンタイムURL、ログイン認証など、パスワードなしでの共有が可能か |
| アクセスログ・追跡機能 | ダウンロード日時・閲覧者・端末情報などを記録できるか |
ポイント:
・取引先に安心して使ってもらえる「安全かつ簡単な添付ファイル共有機能」が導入の決め手になります。
以上の7つの観点をもとに、自社の業務形態・リスク・IT体制を照らし合わせて比較検討することで、失敗しないメールセキュリティソフトの選定が可能になります。
【2025年版】おすすめメールセキュリティソフト比較表(法人向け)

ここでは、数あるメールセキュリティソフトの中から3つを選び、機能や特徴を比較してみましょう。
| 製品名 | 提供形態 | 主な機能 | 価格目安 | サポート | 特徴 | おすすめ企業 |
| 使えるメールバスター | クラウド型 | ・ウイルスフィルタ ・迷惑メールフィルタ ・IPアドレスフィルタ ・添付ファイルの制限 ・アドレスフィルタ ・DMARCチェックフィルタ ・送信ドメイン認証フィルタ ・迷惑メール送信防止機能 ・ウェブ管理システム画面 | 初期費用無料、月額11,770円(1年契約プラン・300ユーザー) | 平日電話・メール・チャット | ・中小企業向け価格と日本語サポート ・スパムメール撃退率は脅威の99.98% ・独自の学習型AIで新たなスパム、ウイルスに対応 | すべての規模に対応 |
| Trend Vision One-Email and Collaboration Security | クラウド型 | ・AIを活用した技術によってなりすまし行為を阻止 ・高度な言語モデリングとアルゴリズムにより、本物のメールと攻撃者によるなりすましメールを区別し、BECを阻止 ・エンドポイント、ネットワーク、クラウド、サードパーティのインテリジェンスなど、幅広い攻撃対象領域による脅威を検出 | 要見積 | 体験版あり | ・Trend Microの統合セキュリティプラットフォーム「Vision One」と連携 ・XDR、EDRとの連携が可能 | ・ゼロトラスト戦略を進めたい企業 |
| m-FILTER | クラウド型 / オンプレミス型 | ・Webの攻撃無害化 ・URLフィルタリング ・シャドーIT対策 ・アンチウイルス ・サンドボックスオプション | ・クラウド版は月額換算1ユーザーあたり500円~ ・オンプレミス型は月額換算1ユーザーあたり250円~ | Web、電子メール、電話 (月~金、9時~18時) | ・国産ソフトで誤送信防止に特化 ・教育機関・自治体に導入実績多数 | ・国内企業、教育機関、自治体 ・誤送信や情報漏えい防止を重視する企 |
特定の課題を解決するメールセキュリティ機能例
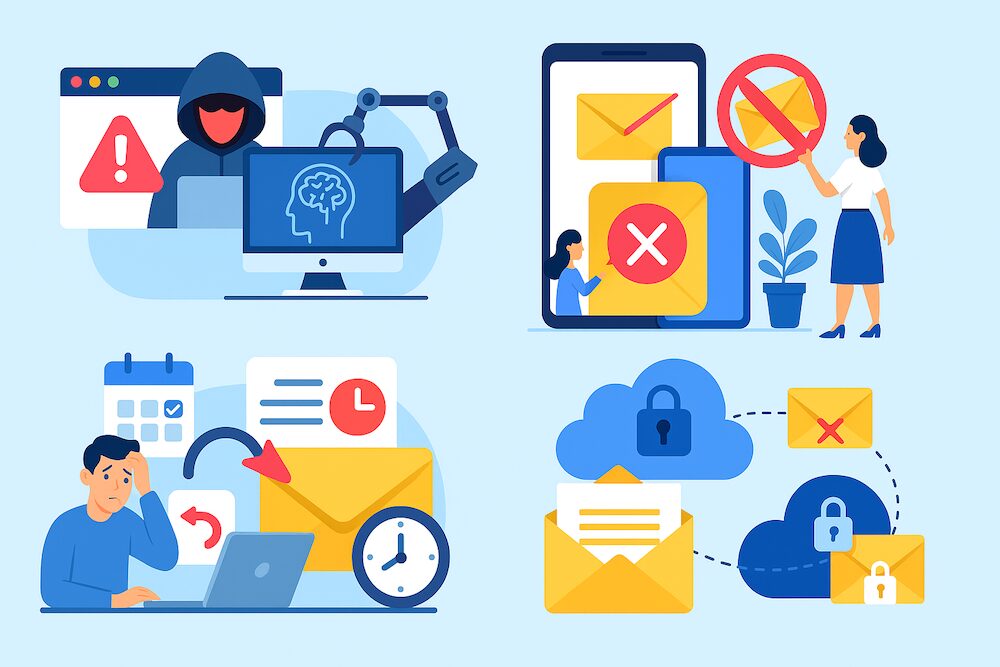
メールを介したサイバーリスクは、単なるスパムを超えて、巧妙な詐欺・マルウェア感染・情報漏えいへと多様化しています。ここでは、企業が抱える具体的な課題に対し、どのようなメールセキュリティ機能が有効かを詳しく解説します。
巧妙化する標的型攻撃メール対策には?
従来のウイルス対策ソフトでは検出できない標的型攻撃メール(APT、BEC、スピアフィッシング等)は、極めて高度かつ個別性の高い手法で攻撃を仕掛けてきます。これらに対応するには、以下のような多層的な防御機能が求められます。
サンドボックス
疑わしい添付ファイルやリンクを仮想環境で実行して検証し、安全性を判断する技術です。ファイルを開く前にその挙動を監視できるため、未知のマルウェアに有効です。
AIによる検知
最新の製品では、AI(機械学習)を活用した振る舞い検知エンジンを搭載しており、通常と異なるメールパターンや言語表現を解析して不審なメールをブロックします。攻撃者の社会的工学手法に対して、機械が高精度に判定するのが特長です。
DMARC等の認証技術
なりすましメールの防止には、SPF(送信元確認)・DKIM(署名認証)・DMARC(認証ポリシー管理)の3点セットが不可欠です。正規ドメインを騙るメールを排除し、信頼性の高い通信基盤を構築できます。
従業員のうっかりミスによる誤送信を防ぐには?
悪意のある攻撃と同様に、従業員の操作ミスによる誤送信も深刻な情報漏えいの原因となります。特に個人情報や社外秘ファイルを含むメールは、送信前のチェック体制が重要です。
送信一時保留機能
送信ボタンを押しても、メールが即時送信されず一定時間保留される仕組みです。その間に内容の再確認や、送信のキャンセルが可能です。
宛先BCC強制変換
複数宛先が入力された場合、自動的にBCCに変換する機能により、他の受信者へアドレスが漏れるのを防ぎます。メルマガや一斉連絡などで有効です。
上長承認フロー
機密性の高い内容や特定の宛先へのメール送信時には、事前に上長の承認を求める機能を設定することで、誤送信に対するダブルチェック体制が整います。
「PPAP」問題を根本から解決するには?
パスワード付きZIPファイルをメール添付し、パスワードを別送する「PPAP」は、今やセキュリティ上のリスクとして問題視されています。攻撃者が両方のメールを傍受すれば容易に解読されてしまうため、より安全でスマートな方法が求められます。
添付ファイルの自動分離とリンク通知
ファイルをメール添付する代わりに、自動的に安全なファイル共有クラウドにアップロードし、受信者にはワンタイムURLを通知する方式が普及しています。期限付き・閲覧回数制限・アクセスログ取得などが可能です。
パスワードレス共有機能
リンクにパスワード不要でアクセスできる設定も可能。代わりにログイン認証や多要素認証と連動させて、安全性と利便性の両立を実現します。
メールセキュリティソフト導入後の運用と注意点

優れたセキュリティソフトを導入しても、それだけで安心するのは早計です。導入後の運用とメンテナンスこそが、セキュリティレベルを維持・向上させるカギとなります。以下のポイントを押さえておくことが重要です。
定期的な設定の見直しとログの確認
・ポリシー設定は業務の変化に応じて見直しが必要です。例:新規部門追加、リモート勤務の拡大など。
・検知ログや送信履歴を定期的に確認し、誤検知・漏れの有無を把握することで精度向上が期待できます。
・管理画面のダッシュボードやレポート機能を活用し、傾向分析・脅威の可視化を進めましょう。
従業員へのセキュリティ教育の実施
・高性能なソフトでも、最終的には「人」の判断が重要です。不審なメールを開かない、リンクを不用意にクリックしないといった基本行動を徹底しましょう。
・フィッシング訓練やセキュリティリテラシー研修を定期的に行い、注意喚起を継続することが推奨されます。
・パスワード管理や多要素認証の推奨も合わせて実施すべき基本対策です。
アップデートと脅威情報の最新化
・クラウド型の製品であっても、設定ポリシーやアラートの見直しは人の手が必要です。
・ベンダーが提供する脅威インテリジェンス(脆弱性情報、攻撃トレンド)を積極的に活用し、対策の質を高めていきましょう。
継続的な効果検証とフィードバック
・単発の導入で終わらせず、年次・半期ごとのレビューを行うことで、運用上の課題や改善点が明らかになります。
・エンドユーザーからの意見も収集し、UI/UXや運用フローの最適化につなげることが重要です。
使えるねっとが提供するメールセキュリティソリューションのご紹介
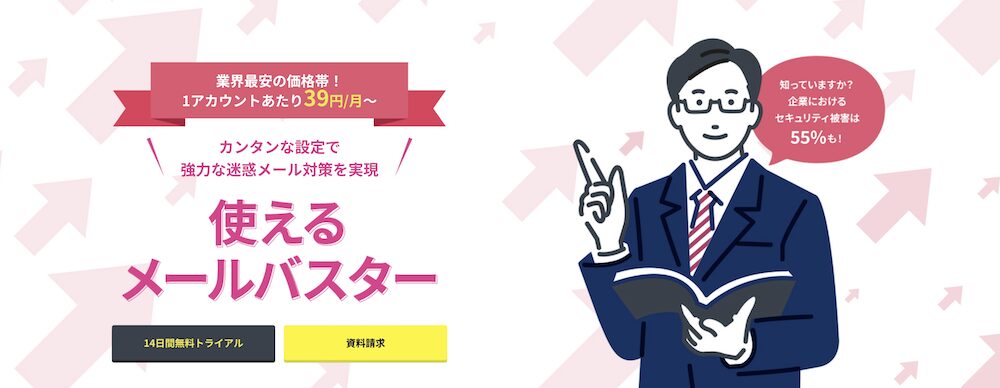
「使えるメールバスター」は、クラウド型で導入が容易、スパム対策からPPAP問題まで幅広くカバーした中小企業向けのセキュリティソリューションです。直感的な管理画面、日本語による手厚いサポート、手頃な価格体系が特徴です。
昨今脅威となっている標的型攻撃メールをはじめ、迷惑メールがメールサーバに届く前にブロック。学習型AI技術のフィルタリングシステムの検出率は99.98%なのに、月額11,770円(年間契約、〜ユーザー数300)で導入可能です。
導入事例:株式会社北里コーポレーション
生殖医療に特化した医療機器メーカー、株式会社北里コーポレーション(静岡県富士市)は、国内外のクリニックを中心に体外受精や卵子凍結向けの製品を提供し、同分野で国内トップシェアを誇ります。同社の業務において、メールは受発注や納期調整など重要なインフラですが、近年スパムやウイルス添付メールの増加が大きな課題となっていました。
「大事な連絡が迷惑メールに埋もれてしまう」「海外からのスパムが特に多く、社内でも限界を感じる」という声があがっていましたが、社内での対応には限界があり、より根本的な対策が求められていました。
そこで同社が導入を決めたのが、クラウド型メールセキュリティサービス「使えるメールバスター」。導入後は、メールボックスから迷惑メールが激減。「そもそも届かなくなる仕組みなので、誤クリックの不安が大幅に減った」と担当者は効果を実感しています。UIのわかりやすさや手軽な運用面も高く評価されており、導入後は特別な研修なしでも社内で問題なく活用されています。
同社では今後、社内サーバのクラウド化も視野に入れ、さらなる業務基盤の強化を進めていく予定です。「使えるメールバスターは、セキュリティと業務効率の両立に向けた第一歩だった」と語る同社の取り組みは、多くの企業にとって示唆に富む事例となるでしょう。
無料トライアルはこちらから
資料請求はこちらから
まとめ

メールは便利な一方で、多くの脅威の侵入口でもあります。自社に合ったメールセキュリティソフトを選ぶことは、情報漏えいや業務停止を未然に防ぐための重要な一歩です。
本記事を通じて、選定のポイントやおすすめ製品の比較ができたことで、自社に最適なソリューションが少しずつ見えてきたのではないでしょうか。
使えるねっとでは、中小企業にも導入しやすいソリューションをご提供しています。まずは無料トライアルから、メールセキュリティの強化を始めてみませんか?
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)