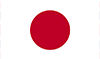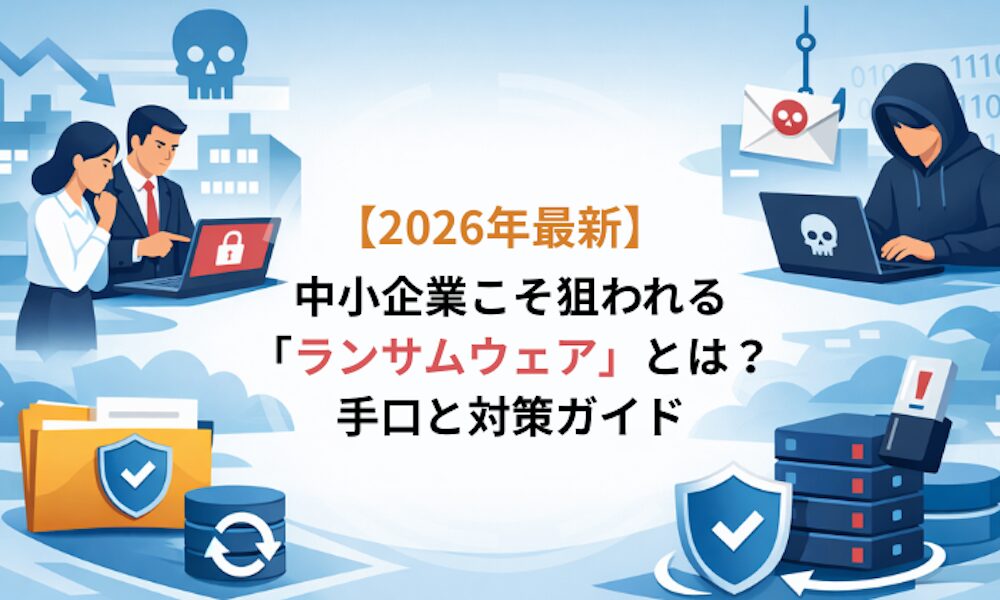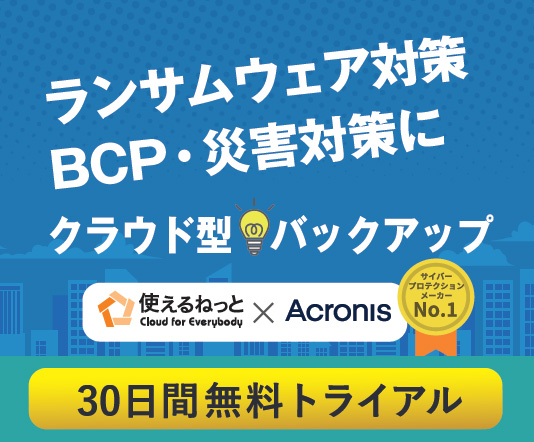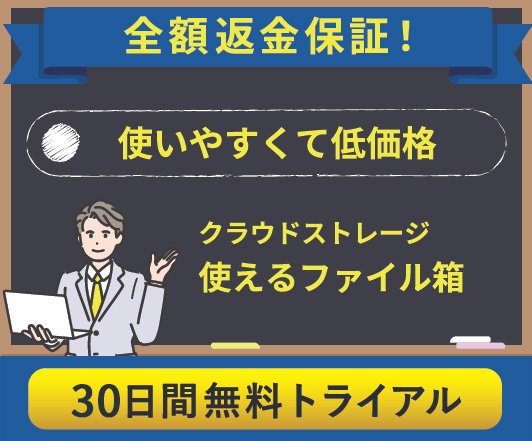サプライチェーン攻撃は、取引先や委託先を経由して企業システムへ侵入する新たな脅威として注目されています。特に中小企業は、コストや人材の制約からセキュリティ対策が後回しになりやすく、大企業への“踏み台”として悪用されるケースが急増中です。一社の脆弱性が取引網全体に波及し、サプライチェーン全体を危険にさらす時代であり、対策は喫緊の課題といえるでしょう。
本記事では、IPAやNISCの最新レポートをもとに、サプライチェーン攻撃の仕組みと中小企業が狙われやすい理由や経営リスクを説明し、限られたリソースの中で実践できる具体的な防御策をわかりやすく解説します。
目次
サプライチェーンを狙った攻撃とは
中小企業が狙われやすい理由
被害がもたらす経営リスク
中小企業が実施すべき対策と管理手法
継続的な改善で企業を守る
サプライチェーン攻撃への備えを経営課題に
FAQ
サプライチェーンを狙った攻撃とは

企業がどれほど自社のセキュリティを強化しても、取引先の防御が甘ければ、そこが“突破口”になります。サプライチェーン攻撃は、こうした企業間の信頼関係を逆手に取る巧妙な手法です。ここでは、その定義と仕組み、そして実際に起きた被害事例から、その脅威の実態を明らかにします。
第三者経由で侵入する新しいサイバー攻撃
サプライチェーン攻撃とは、企業が直接攻撃されるのではなく、取引先や外部委託先など「第三者」を経由して侵入されるサイバー攻撃のことを指します。たとえば、ソフトウェアのアップデート機能にマルウェアを仕込んで配布したり、業務委託先の従業員を装ったフィッシングメールを送信して認証情報を盗み取ったりする手口が代表的です。
IPA(情報処理推進機構)はこれを「サプライチェーンを構成する企業・団体間の信頼関係を悪用して、間接的に標的組織へ侵入する攻撃」と定義しています。
攻撃者はまず、セキュリティ対策が不十分な中小企業や外注先を侵入経路として選びます。そこからVPNや共有サーバなどの接続経路をたどり、最終的に大企業や官公庁などの中枢ネットワークにアクセスします。いわば「本命に直接攻撃を仕掛けず、外堀から崩す」戦略です。
その背景には、クラウド化・DX化によって企業間のデータ共有が急速に進んだことがあります。業務効率化の一方で、一社でも防御が甘いと全体が危険にさらされるという新たなリスク構造が生まれています。
実際の被害事例とその影響範囲
この種の攻撃は国内外で急増しており、被害の規模も拡大しています。代表的な例として挙げられるのが、2020年に発生した米SolarWinds社のサプライチェーン攻撃事件です。同社のネットワーク管理ソフトの更新プログラムに不正コードが混入され、世界中の約1万8,000の機関が影響を受けました。
日本でも2022年以降、自動車メーカーの取引先企業サーバを経由した情報漏えい、製造業の設計データ流出など、サプライチェーンを起点とする事件が相次いでいます。これらは一見すると小規模なシステム障害に見えても、取引先を巻き込み、生産停止・納期遅延・顧客信用の失墜といった連鎖的被害に発展しました。
つまり、サプライチェーン攻撃は「大企業を狙った事件」に見えて、実際には中小企業が最初に被害を受け、最も深刻なダメージを負う構造なのです。
中小企業が狙われやすい理由

サプライチェーン攻撃の多くは、最初の侵入口として中小企業が狙われています。防御の弱点を突破すれば、取引先の大企業ネットワークにまで到達できるためです。ここでは、攻撃者が中小企業を標的に選ぶ背景と、その構造的な脆弱性を見ていきましょう。
セキュリティ投資・人材不足による防御力低下
中小企業が狙われる最大の理由は、セキュリティ投資と人材リソースの不足にあります。IPAの「2024年度中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査報告書」によると、中小企業のうち、約7割が「組織的なセキュリティ体制が整備されていない」と回答しています。専任部署を置けないため、IT担当者が本業と兼任でセキュリティ管理を行っているケースが多く、脆弱性対応やログ監視などの運用が後回しになりがちです。
また、コスト面からセキュリティ製品の導入や定期更新を見送る企業も少なくありません。ウイルス対策ソフトは導入していても、ファイアウォール設定やアクセス制御、ゼロトラスト導入といった高度な防御施策は手付かずという状況が多く見られます。
その結果、攻撃者にとって中小企業は「侵入しやすく、価値のあるデータに近い」理想的なターゲットになるのです。特に、クラウドストレージやグループウェアなど、外部と常時接続しているサービスが多い企業ほど、リスクは高まります。
加えて、セキュリティ人材の採用難も深刻です。大企業に比べ報酬・育成機会が限られるため、専門知識を持つ人材が定着しにくいという構造的課題を抱えています。結果として、パッチ未適用のまま放置された端末や、不正アクセス検知の遅れが攻撃成功の要因となっています。
取引先との接続点が多いリスク構造
中小企業が抱えるもう一つの大きな脆弱性は、取引先企業とのシステム接続点の多さです。
EDI(電子データ交換)やファイル共有、クラウド会計・在庫管理など、取引先とリアルタイムでデータをやり取りする仕組みは、業務効率化の裏で「攻撃の経路」にもなり得ます。攻撃者は、まず防御が緩い企業のネットワークに侵入し、その接続経路をたどって大企業の基幹システムへと到達するのです。
たとえば、製造業や物流業では、取引先との共有サーバやVPNを通じて設計図や受発注データをやり取りすることが一般的です。この「共有環境」こそがサプライチェーン攻撃の温床になります。さらに、アクセス権限管理が曖昧なまま、複数の社員が同じID・パスワードを利用しているケースも多く、攻撃者にとっては“裏口”を発見するのが容易になります。
被害がもたらす経営リスク

サプライチェーン攻撃による被害は、単なる情報漏えいにとどまりません。業務停止、取引停止、信頼喪失、そして法的責任の発生など、企業経営を揺るがす深刻な結果をもたらします。ここでは、実際に中小企業が直面する主要なリスクを整理します。
社会的信用の失墜と取引先への影響
サイバー攻撃で最も深刻なのは、「社会的信用の失墜」です。
一度の情報漏えいが、長年築いてきた取引先からの信頼を一瞬で奪い去ります。特にサプライチェーン攻撃では、被害が取引先にも波及するため、「自社だけの問題」では済みません。
たとえば、受発注システムが停止すれば納期遅延が発生し、顧客企業の生産ラインにも影響を及ぼします。結果として、契約解除や新規案件の停止など、事業継続に直結する損害が生じます。
IPAの「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」でも、「情報漏えいの場合は、顧客や取引先の信頼を失い、業績が悪化することもあります」と警鐘を鳴らしています。実際に、国内の製造業では、外注先の情報漏えいをきっかけに大手取引先から取引停止を通告されたケースもあります。
被害を受けた企業が意図せず「攻撃の踏み台」となった場合でも、「監督責任が果たされなかった」として非難を浴びかねません。社会からの評価は厳しく、一度の事故がブランド価値・採用力・資金調達力の低下といった中長期的ダメージを引き起こします。
法令遵守・賠償リスクの増大
もう一つの深刻なリスクが、法令違反や損害賠償請求への発展です。
個人情報を扱う企業で情報漏えいが発生した場合、個人情報保護法に基づき、個人情報保護委員会への報告義務と本人への通知義務が課されます。これらの対応には多大な時間とコストがかかるうえ、メディア報道によって社会的信用がさらに低下する可能性もあるのです。
また、取引契約の中には「情報管理義務」や「秘密保持条項」が含まれていることが多く、漏えい事故は契約違反とみなされることがあります。その結果、取引先から損害賠償を請求されるケースも珍しくありません。
中には、委託先の過失による情報漏えいで数千万円規模の賠償金が発生した事例もあります。さらに、クラウドサービスや外部ストレージを利用していた場合、その設定ミスが原因でも、法的責任は利用企業側に問われかねません。
監督官庁も、こうしたリスクに対し企業に説明責任を求めています。たとえば、経済産業省は2026年10月以降に「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の施行を予定しており、企業のセキュリティレベルを評価し、企業間の比較やサプライチェーン全体を強化することも目指しています。
中小企業が実施すべき対策と管理手法

サプライチェーン攻撃を防ぐには、単発の対策ではなく「継続的な管理と改善の仕組み」が不可欠です。ここでは、NIST CSF(サイバーセキュリティフレームワーク)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)に基づく、実践的で効果的な4つの対策を紹介します。
ゼロトラストセキュリティの導入
従来の「社内は安全・社外は危険」という境界防御の考え方は、クラウド利用やリモートワークの普及により通用しなくなりました。そこで注目されているのが、ゼロトラストセキュリティです。
ゼロトラストの基本理念は、「誰も何も信用しない」。すべてのアクセスを検証し、認証・認可を通過した通信のみを許可する仕組みを構築します。たとえば、VPN経由でも利用者の端末や場所に応じてアクセス制限を設ける「多層認証(MFA)」や、「最小権限アクセス」の設定が有効です。
中小企業でも、クラウドサービスの管理画面からゼロトラストに近い設定を行うことが可能で、段階的導入が現実的な選択肢となります。
メールゲートウェイ・DMARCによる防御
サプライチェーン攻撃の多くは、メールを起点とするフィッシングやマルウェア拡散から始まります。
まず導入したいのが、メールゲートウェイ(セキュリティメールサーバ)です。受信段階で不審な添付ファイルやURLを自動スキャンし、危険メールを隔離します。
さらに、送信ドメイン認証技術であるSPF・DKIM・DMARCを設定すれば、なりすましメールを高精度で検出できます。これにより、取引先や社内ユーザーを装った詐欺メールを防ぐことができるのです。
最近では、クラウド型のゲートウェイサービスも多く、専用サーバを持たない中小企業でも手軽に導入可能です。
外部委託先のセキュリティ監査
サプライチェーンの一部として信頼を保つには、取引先・委託先のセキュリティ水準を管理することが欠かせません。
具体的には、契約書にセキュリティ要件を明記し、外部委託先に定期的な自己点検や第三者監査を求めることが推奨されます。チェックリスト形式で通信暗号化・アクセス権管理・ログ保管・外部媒体利用ルールなどを確認し、定期的に更新することで、「取引先も含めた防御体制」を構築できます。
社員教育・標的型攻撃訓練の強化
多くのサイバー攻撃は、最終的に「人」を狙います。たとえシステムが堅牢でも、従業員が不審メールを開封したり、パスワードを使い回したりすれば防御は破られます。そこで欠かせないのが、社員教育と標的型攻撃訓練です。
年1回の座学研修だけでなく、実際に偽装メールを送って対応をチェックする「疑似攻撃訓練」や、フィッシング事例を社内共有する仕組みが効果的です。
また、NIST CSFの「Protect(防御)」領域では、教育をセキュリティマネジメントの中心要素と位置づけています。社員のITリテラシーが向上すれば、組織全体の防御レベルが自然に底上げされるのです。
継続的な改善で企業を守る

セキュリティ対策は一度導入すれば終わりではありません。技術や攻撃手法は日々進化し、今日の安全が明日の脆弱性になることもあります。重要なのは、対策を「仕組み化」し、継続的に改善できる体制を整えることです。
ここでは、そのための5つの実践アプローチを紹介します。
経営層が主導するセキュリティガバナンスの確立
サイバー攻撃への備えは、もはやIT部門だけの責任ではありません。企業全体のリスクマネジメントの一環として、経営層が主導して取り組む姿勢が欠かせません。
まず重要なのは、セキュリティを「コスト」ではなく「経営リスクに対する投資」として位置づけることです。経営層が方針を明確に打ち出し、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)やNIST CSF(サイバーセキュリティフレームワーク)を基に、組織全体で共通のポリシーを策定することが求められます。
これにより、セキュリティ目標・責任範囲・意思決定プロセスが明文化され、社員一人ひとりが自分の役割を理解した上で動けるようになります。トップが旗を振ることで、セキュリティが企業文化の一部として根づいていくのです。
PDCAサイクルによる継続的な改善
セキュリティレベルを維持・向上させるためには、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルの定常化が不可欠です。
まず「Plan」でリスクアセスメントを実施し、脅威や脆弱性を洗い出して対策方針を立案します。「Do」で施策を実行し、「Check」で監査・評価を実施。最後に「Action」で改善策を反映し、運用ルールや教育内容を更新します。
このサイクルを半年や年単位で繰り返すことで、脆弱性を早期に発見・修正し、再発防止につなげることができるのです。
IPAはこの「継続的改善」を「セキュリティ成熟度向上の鍵」と位置づけており、点検を一過性で終わらせず、常に最新の脅威環境に追随する柔軟性が求められます。
インシデント対応体制と訓練の定期実施
万が一の攻撃に備え、インシデント対応体制を明確化しておくことも重要です。
被害発生時には「誰が」「どの順番で」「何を行うか」の迅速な判断が求められます。そのためには、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)や担当者を中心とした、対応手順書の整備と定期訓練の実施が効果的です。
実際のランサムウェア感染や情報漏えいを想定した模擬訓練を行うことで、初動対応力や判断スピードが向上します。さらに、訓練後には振り返りを行い、課題をリスト化して次回改善につなげる―これが「実効性ある体制」の基本です。
サプライチェーン全体での情報共有と連携
サイバー攻撃は一社だけで防ぎきれるものではありません。特にサプライチェーン攻撃では、取引先・委託先との連携こそが最大の防御策です。
自社のセキュリティ情報を積極的に共有し、合同訓練やベンダー監査を通じて連携を強化することで、全体の防御レベルを底上げできます。たとえば、脅威情報共有プラットフォーム(ISACなど)への参加や、共同でのフィッシング対策研修などは有効な取り組みです。
こうした「横のつながり」が生まれることで、単一企業では気づけない攻撃パターンを早期に発見でき、連鎖的被害の未然防止につながります。
外部リソース・クラウドサービスの有効活用
人材や予算が限られる中小企業では、外部の専門リソースを活用することが現実的な選択肢でしょう。
たとえば、外部SOC(セキュリティオペレーションセンター)を利用すれば、24時間365日の監視体制を専門家に委託でき、異常検知やログ分析を自動化することが可能です。
また、クラウド型セキュリティサービスの導入で、最新の脅威情報やAI分析を即座に反映、自社での運用負担を大幅に軽減できます。
これらの外部支援を「補助輪」として取り入れ、必要に応じて自社運用へ段階的に移行する―それが、持続可能なセキュリティ経営への現実的なアプローチです。
このように、サイバーセキュリティの本質は「守る仕組みを継続的に育てること」にあります。経営層のリーダーシップ、現場の実践力、そして外部との協働が三位一体となってこそ、企業は変化する脅威の中で強靭な体制を築けるのです。そして、万が一に備えたバックアップを加えることで、万全のセキュリティシステムを実現できます。
サプライチェーン攻撃への備えを経営課題に

サプライチェーンを狙った攻撃は、もはや大企業だけの問題ではありません。
取引網は大小さまざまな企業で構成されており、どこか一社でも防御が甘ければ、全体が脆弱化します。特に中小企業は、サプライチェーンの中で「重要な接続点」としての役割を担っているため、そのセキュリティレベルが取引全体の信頼性を左右します。
中小企業にとって、セキュリティ投資は「コスト」として見られがちです。しかし、万が一の被害による損失や業務停止のリスクを考えれば、「守るための経営投資」こそ最も費用対効果が高い支出なのです。
攻撃者は、システムの強度よりも“油断”を突きます。更新を怠ったソフトウェアや、ルールが形骸化した管理体制こそが、最大の脆弱性です。だからこそ、経営層がリーダーシップを取り、全社でセキュリティ意識を共有し、継続的に改善する文化を根付かせることが求められます。
その第一歩として重要なのが、「万が一に備えて事業データを確実に守る仕組みの構築」です。運用ルールの強化だけでは、ランサムウェア、内部不正、端末故障といったデータそのものへの被害を完全に防ぐことはできません。ビジネスを止めないためには、攻撃を受けても “すぐに元に戻せる” ことが何より重要です。
たとえば、使えるねっとが提供する「使えるクラウドバックアップ」は、以下のような特徴を備えています。
・自動バックアップで担当者の負担なし
・ランサムウェア感染時も復元可能
・世代管理で過去データも安全に保存
・容量追加も柔軟、初期投資不要のクラウド型
サプライチェーン全体を守ることは、自社を守ることでもあります。一社一社がセキュリティを「経営課題」として位置づけ、持続的な対策を積み上げることで、取引網全体の信頼性と競争力を高めることができるのです。
安全なサプライチェーンの構築とレジリエンスの向上のために、信頼と実績のクラウドサービス「使えるクラウドバックアップ」をぜひご検討ください。
FAQ
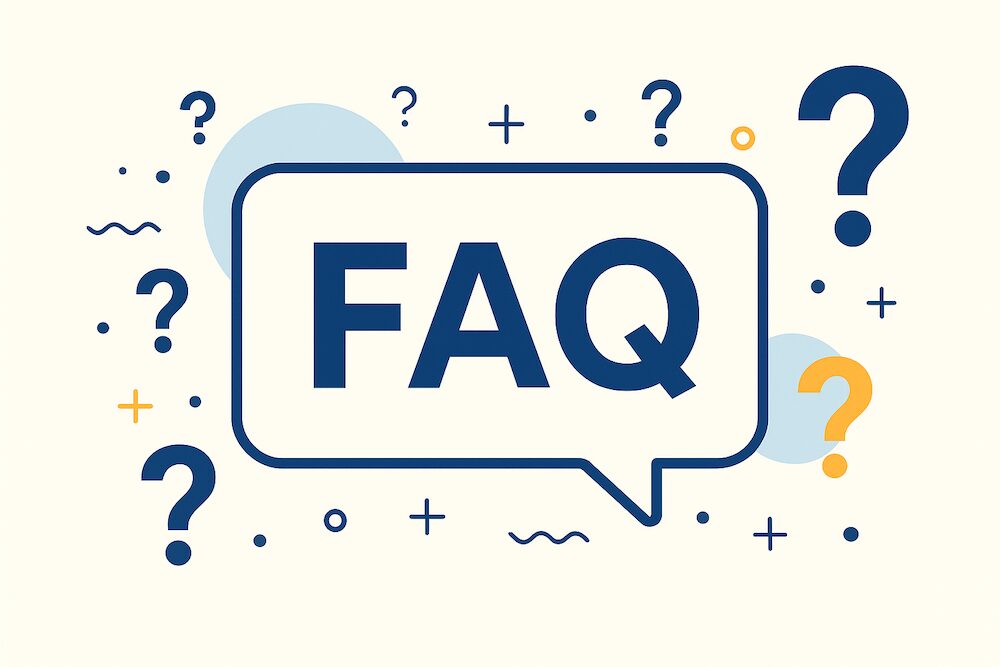
なぜ中小企業がサプライチェーン攻撃の標的になりやすいのですか?
中小企業は、セキュリティ担当者や専門ツールが不足しており、更新・監視体制が不十分なことが多いからです。攻撃者にとっては「防御が弱く、取引先ネットワークに接続できる企業」が最も狙いやすい対象になります。
クラウドサービスの利用は安全ですか?
適切な設定と信頼性の高いサービスを選べば、むしろ安全性は向上します。たとえば「使えるクラウドバックアップ」のように、暗号化通信・高度なランサムウェア対策などを備えたサービスなら安心でしょう。
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)