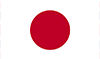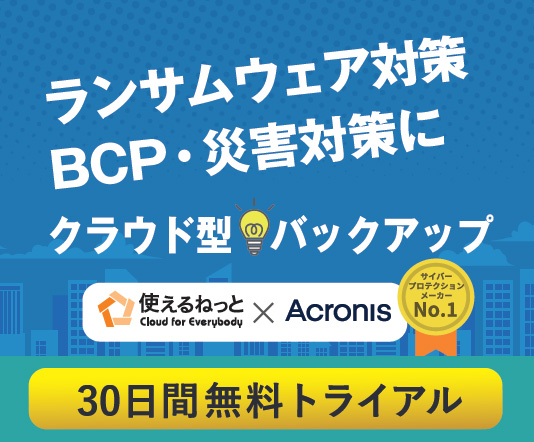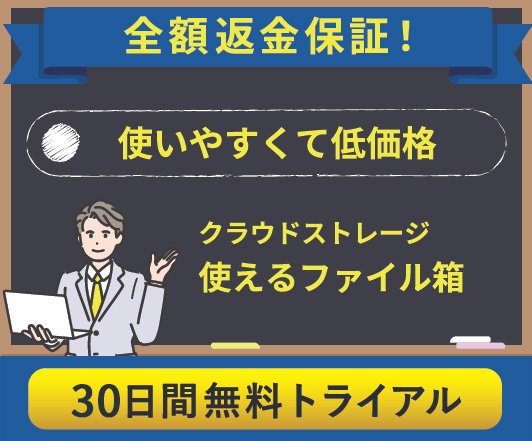スパムメールは「迷惑な広告」ではなく、ランサムウェア感染や不正送金、情報漏えいを引き起こす重大な経営リスクです。最近は、実在企業を装った巧妙な標的型メールが増え、従業員の注意力だけで防ぐのは難しくなっています。
本記事では、中小企業が押さえるべき、次のポイントを解説します。
1. スパムメールの最新手口とビジネスリスク
2. 従業員でも実践できる具体的な見分け方
3. 中小企業が取るべき「組織的・システム的」対策
使えるねっとは、長年にわたりクラウド・ホスティングやメールセキュリティサービスを提供してきた企業として、数多くの中小企業のセキュリティ課題を支援してきました。本記事では、現場知見にもとづき、実務に役立つ具体策をわかりやすく紹介します。
目次
スパムメール(迷惑メール)とは?
放置は危険!スパムメールが引き起こす中小企業の「経営リスク」
【図解】スパムメールの主な種類と巧妙な手口
従業員ができる!スパムメールの見分け方と対処法(個人レベル)
会社として導入すべきスパムメール対策(組織・システムレベル)
(補足)自社が「加害者」にならないための法律知識
まとめ
FAQ
スパムメール(迷惑メール)とは?

ここではスパムメール(迷惑メール)とは何か、なぜ中小企業のもとに送られてくるのかについて解説します。
スパムメールの定義と送信者の目的
スパムメールとは、受信者の同意なしで、一方的に大量送信される迷惑メールのことを指します。本来は広告・宣伝目的のメールが中心でしたが、近年はより悪質な目的へと急速にシフトしています。
現在広がっているスパムメールの多くは、企業の金銭や情報を狙ったサイバー攻撃の一環です。たとえば、ログイン情報を盗むフィッシング詐欺、添付ファイルを通じたマルウェア・ランサムウェア感染、経理担当者を狙う不正送金(BEC)、そして取引先情報や設計データなどの機密情報窃取が挙げられます。
つまりスパムメールは、「邪魔な広告」から「企業の弱点を突く攻撃ツール」へと変化しており、中小企業も狙われやすい状況になっています。
なぜ自社にスパムメールが届くのか?(主な経路)
「うちは有名企業ではないから狙われない」と考える中小企業は少なくありません。しかし現実には、規模に関係なくメールアドレスが収集され、攻撃対象として組み込まれることが一般的です。
スパムメールが届く主な経路は次のとおりです。
| Webサイトからの自動収集 | 会社概要・お問い合わせフォーム・採用ページなどに掲載されたメールアドレスは、スクリプトによって自動的に収集される |
| 名簿流出・漏えい | 過去に登録したサービス、取引先企業、業務委託先から情報が漏えいすることで、第三者にメールアドレスが渡るケースがある |
| ドメイン名からの推測(ランダム生成) | 「info@」「support@」「sales@」などは多くの企業で使われるため、攻撃者が自動生成して総当たりで送ることが可能 |
このように、メールアドレスがどこかで公開・流出・推測されるだけで、規模を問わずスパムメールは届いてしまいます。中小企業こそ、受信段階での防御が重要です。
放置は危険!スパムメールが引き起こす中小企業の「経営リスク」

スパムメールは、単に「従業員が気をつければよい」レベルの問題ではありません。添付ファイルを開いた、URLをクリックした—それだけで企業全体の業務がストップし、取引先へ甚大な影響が及ぶケースが現実に増えています。
ここでは中小企業が特に直面しやすい3つのリスクを解説します。
リスク1:ランサムウェア感染による「業務停止」と「身代金要求」
スパムメールの添付ファイルやリンクからマルウェアが侵入すると、社内PCやサーバ内のデータが一気に暗号化され使用不能になります。これがランサムウェア攻撃です。
暗号化が完了すると、画面には「復旧したければ身代金を支払え」という脅迫メッセージが表示され、見積書・顧客情報・設計データなど、すべての業務データが「人質」になります。復旧まで数日〜数週間、完全に業務停止することも珍しくありません。
被害を防ぐには、社内だけに依存しないクラウドバックアップの併用が重要です。
リスク2:フィッシング・不正送金による「金銭的被害」
スパムメールの中には、従業員のID・パスワードを盗むフィッシング詐欺が多数紛れています。ネットバンキングや業務システムに不正ログインされると、口座残高が一瞬で引き抜かれることもあります。
さらに中小企業で増えているのが、経営者や経理担当者を狙ったビジネスメール詐欺(BEC)です。取引先の担当者になりすまし、「振込先口座が変更になりました」と巧妙な文面で誘導し、偽の口座へ数百万円〜数千万円が不正送金されてしまうケースが後を絶ちません。BECは「メールが本物に見える」ため、注意力での防御が極めて難しい攻撃です。
ビジネスメール詐欺(BEC)とは?SPF・DMARCなど簡単に導入できる対策を解説
リスク3:機密情報・顧客情報の漏えいによる「信用の失墜」
スパムメール経由で侵入した攻撃者は、社内に保存された機密情報・顧客情報を盗み出すことがあります。情報が漏えいすると、個人情報保護法にもとづく報告義務や行政指導など、法的リスクが発生するだけではありません。
中小企業にとって最も深刻なのは、失われた信用の回復が極めて難しいことです。「この会社は情報管理が甘い」と判断されれば、取引停止・契約見直し・評判の低下といった取引先への二次被害が一気に広がり、売上や採用にも長期的な影響が出てしまいます。
【図解】スパムメールの主な種類と巧妙な手口

スパムメールにはいくつかのパターンがありますが、いずれも「本物そっくりの文面」で受信者を騙す点は共通しています。ここでは中小企業が特に遭遇しやすい3つの手口を紹介します。
【手口1】不特定多数を狙う「ばらまき型」スパム
大量に送信される典型的なスパムメールです。古くからある手口ですが、依然として被害は続いています。
【代表的な例】
・ウイルス付き添付ファイル(請求書・領収書風)
| 件名:ご請求書送付の件 添付ファイル:Invoice_2025.zip 内容:「至急ご確認ください」 |
・架空請求
| 件名:利用料金の未払いが発生しています 内容:「本日中にご連絡がない場合、法的措置を取ります」 |
・当選商法・広告宣伝
| 件名:おめでとうございます!当選しました! 内容:怪しいURLへ誘導 |
【手口2】中小企業が最警戒すべき「標的型攻撃メール」
最も危険で、中小企業の被害が増えているのがこの「標的型攻撃」です。
ばらまき型の対象が不特定多数なのに対し、標的型攻撃は特定の企業・部署・個人を狙い撃ちします。攻撃者は業務内容や取引関係を事前に調査し、「開かないと仕事が進まない」メールを装います。
【巧妙な手口の例】
・取引先になりすます(Emotetが使う“返信型”)
| 件名:Re: 先日の件について 内容:実際のメールの返信に見える、添付ファイルがマルウェアに置き換えられている |
・公的機関の偽装(税務署・保健所・警察など)
| 件名:【重要】税務調査に関するご連絡 内容:偽サイトへ誘導しID・パスワードを入力させる |
・開かざるを得ない件名(請求書・契約書更新など)
| 件名:契約更新のお知らせ 添付:Contract_2025.pdf(実際はマルウェア) |
また、取引先や社内担当者を装って振込口座を変更させるBEC(ビジネスメール詐欺)も標的型攻撃の一種です。「本物にしか見えない」ため、注意だけでは防げないのが最大の脅威です。
【手口3】ID・パスワードを盗む「フィッシングメール」
外部サービスのログインページを偽装し、従業員のID・パスワードを盗む攻撃です。
【よくある偽装パターン】
・Microsoft 365
| 件名:パスワードの有効期限が切れます 内容:URL:login-microsoft365-security[.]com |
・Google Workspace
| 件名:アカウントに不審なログインがありました 内容:「詳細を確認する」ボタン → 偽ログインページへ |
・銀行・クレジットカード会社
| 件名:【緊急】口座がロックされています 内容:「本人確認」の名目で情報入力を要求 |
実際のページと区別がつかないほど精巧なため、URLの微妙な違いに気づけないと簡単に情報を盗まれてしまいます。
従業員ができる!スパムメールの見分け方と対処法(個人レベル)

スパムメールは、どれだけ組織的な対策を行っても「最後の砦」は現場の従業員です。とはいえ、専門知識がなくても、ちょっとしたポイントを押さえるだけで多くの攻撃を未然に防ぐことができます。ここでは、今日から実践できる7つのチェックポイントと、誤って開封・クリックしたときの対処法を紹介します。
怪しいメールを見分ける7つのチェックポイント
スパムメールの多くは「本物らしく見せる工夫」を凝らしていますが、よく見ると必ず「違和感」が潜んでいます。以下の7つを順番にチェックしてみてください。
1. 送信元アドレスを必ず確認する
見た目は正しく見えても、ドメインが微妙に違うだけで偽物の場合があります。以下の例が示す通り、一文字違いの「そっくりドメイン」は極めて多く使われます。
例:
・正規:@tsukaeru.net
・偽装:@tsukaeru-net.com、@tsukaeru.coなど
2. 件名が「緊急」「警告」「パスワードリセット」など不安を煽る
攻撃メールは、受信者に冷静な判断をさせないため、「アカウントがロックされました」「緊急のご確認が必要です」など、心理的に焦らせる件名が多く使われます。
3. 宛名が不自然(「お客様各位」「メールユーザー様」など)
本来の取引先なら、あなたの氏名や会社名を正しく記載するはずです。不特定多数への一斉送信である証拠として、曖昧な宛名が使われることがよくあります。
4. 本文の敬語・漢字・レイアウトに違和感がある
・敬語が過剰、もしくは不自然
・漢字が簡体字に近い
・フォントが部分的に異なる
・段落のスペースがおかしい
こうした不自然な日本は、海外の攻撃者が自動翻訳を使用しているケースで特に顕著です。
5. リンク(URL)の“本当の行き先”を確認する
本文に表示されたURLと、マウスオーバーしたときの実際のリンク先が異なることがあります。
例:
・表示:https://login.microsoft.com
・実際:https://login-micro-soft-security[.]com
わずかな違いでも、偽サイトである可能性が非常に高いです。
6. 添付ファイルの拡張子が危険(.zip .exe .htmなど)
特に注意すべき添付ファイル例:
・.zip…解凍後にウイルスが仕込まれている
・.exe…実行ファイル(ほぼ100%危険)
・.htm / .html…偽ログインサイトへ誘導されるケース多数
業務上「開くべきファイルか?」を必ず一度立ち止まって考えましょう。
7. 署名に会社情報がない、電話番号が架空
信頼できる企業のメールには、必ず住所・電話・担当部署が記載されています。スパムメールでは、架空の住所、存在しない電話番号、極端に簡素な署名が使われることがあります。
もしスパムメールを開封・クリックしてしまったら?
どれだけ注意していても、人間はミスをします。大切なのは「ミスしたあと、いかに被害を最小化するか」です。誤ってクリックしてしまった場合は、次の3ステップを“すぐに”実行してください。
1. ネットワークから切断する
まず被害拡大を防ぐため、端末をオフラインにします。
・LANケーブルを抜く
・Wi-Fiをオフにする
・VPN接続を切断する
感染拡大(社内共有フォルダ・NASなど)を防ぐために最も重要です。
2. パスワードを変更する(入力してしまった場合)
フィッシングサイトでID・パスワードを入力した場合は、即座に変更してください。同じパスワードを他サービスで使い回していた場合は、それらもすべて変更が必要です。
3. 上司または情報システム部門へすぐ報告する
恥ずかしさや不安から「黙ってしまう」ケースが最も危険です。初期対応が遅れれば遅れるほど、ランサムウェアの横展開、情報漏えい、取引先への被害のリスクが高まります。
中小企業は特に、事前に「報告フロー」を決めておくことが重要です。たとえば、「怪しいメール → 部署長 → 情報システム部門 → 経営陣」というように、最低限の流れを定めておくだけでも、被害を最小限に抑えられます。
会社として導入すべきスパムメール対策(組織・システムレベル)

従業員の注意力は、スパムメール対策の重要な要素といえます。しかし、攻撃は年々巧妙化しており、人間の注意だけで100%防ぐのは不可能です。企業は「人は必ずミスをする」という前提で、ミスが起きても被害が広がらない「仕組み(システム)」を整えることが経営者の責務です。ここでは、中小企業が段階的に導入すべき組織的・システム的対策を解説します。
対策①:人的・組織的対策(基本の「き」)
最初に整えるべきなのは、技術よりも「社内の仕組み」です。具体的には、以下の取り組みが基本です。
・従業員教育の定期化
標的型攻撃の例や、実際に届いたスパムメールを題材にした学習は効果的です。
・セキュリティポリシー(社内ルール)の策定
「怪しいメールは開かない」「不審な場合は即報告」など、最低限のルールを明文化します。
・報告体制の確立
事故発生時のフロー(例:従業員 → 部署長 → 情シス → 経営者)を決めておくことで、被害拡大を防げます。
・標的型メール訓練の実施
実際に“偽の訓練メール”を送り、従業員の反応をチェックする方法です。開封率・クリック率が可視化され、改善点が明確になります。
これらはシステム導入の前提となる「土台」であり、どんな企業でも必ず取り組むべき領域です。
対策②:クライアント側(PC端末)での対策
次に必要なのが、各従業員のPCを守るための基本対策です。
・セキュリティソフトの導入と最新化
マルウェア感染を防ぐ“最後の砦”になります。
・OS・アプリのアップデート
古いOSは脆弱性が多く、攻撃者に狙われやすい状態です。
・メールソフトのフィルタリング設定
迷惑メール判定機能を活用するだけでも一定の効果があります。
ただし、これらはあくまで端末に届いてしまった場合の対策です。理想は、危険なメールがPCに届く前にブロックすること、ここからが最も重要な領域です。
対策③:【中小企業に推奨】ゲートウェイ(入口)での対策
スパムメールを根本的に減らすには、メールサーバに届く前(ゲートウェイ)で脅威を遮断する仕組みが不可欠です。クラウド型メールセキュリティは、受信前にスパム・ウイルスを検知し、危険なメールを隔離します。
UTMにもメール保護機能はありますが、ファイアウォールやVPNなど多機能ゆえに管理が複雑ですし、「メール専門」ではないため、最新スパムへの対応が遅れるという弱点があります。
これに対して、クラウド型メールセキュリティは、専任担当者不要なので管理が圧倒的に楽です。また、初期費用を抑えることができ、サブスクリプションで導入しやすいというメリットもあります。さらに、クラウド型なら新種ウイルス・最新攻撃手口へ常に自動対応が可能です。
使えるねっとの「使えるメールバスター」は、まさに中小企業向けに最適化されたクラウド型メールセキュリティで、既に多くの企業の「入口防御」を支えています。
対策④:「なりすまし」を防ぐ送信ドメイン認証(SPF, DKIM, DMARC)
スパム対策は「受信」を守るだけではありません。自社ドメインそのものが「なりすましメールの発信源」として悪用されないよう、送信側の対策も不可欠です。
・SPF:メールの「送信元住所(IPアドレス)」が正しいか確認する仕組み
・DKIM:メールが途中で改ざんされていないことを証明する「電子署名」
・DMARC:SPF・DKIMをチェックし、失敗したメールを「拒否」するなどの方針を宣言する仕組み
これらは、自社ドメインの信頼性を守るための必須設定です。使えるねっとのホスティングサービスはこれらの設定にも対応しており、専門知識がなくても導入できます。
(補足)自社が「加害者」にならないための法律知識
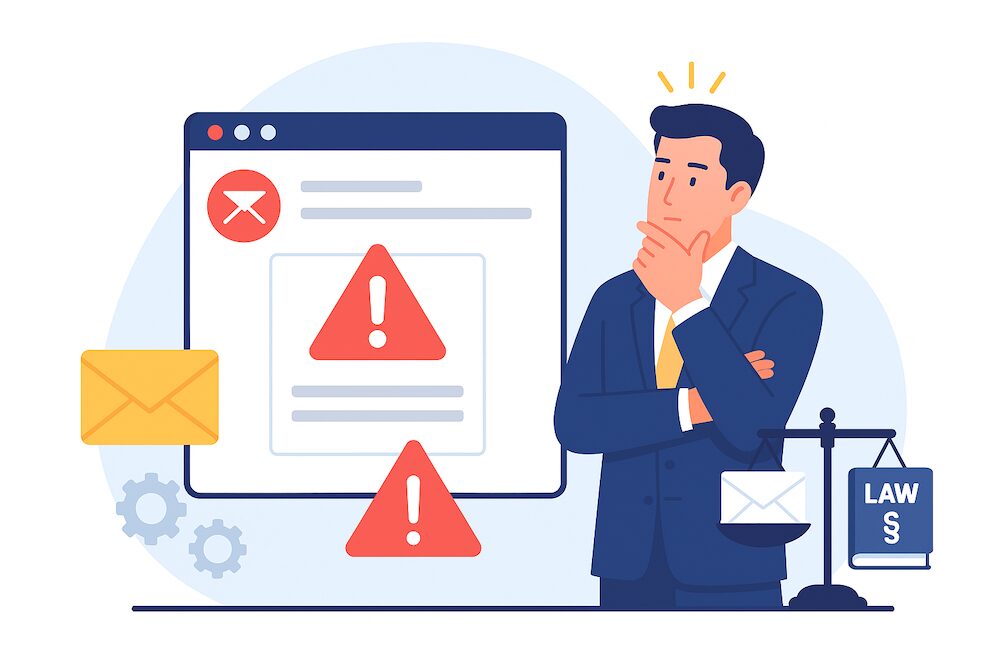
スパムメールと聞くと「受信側」の問題に意識が向きがちですが、企業として注意したいのは、自社が意図せず「スパム送信者」とみなされてしまうリスクです。営業メールやメルマガを送る際には、必ず特定電子メール法を守る必要があります。
この法律では、オプトイン(事前同意)が大原則です。
受信者が「受け取ることに同意している」場合にのみ、広告・宣伝を目的としたメールを送信できます。名刺交換をしただけ、問い合わせフォームから連絡があっただけでは「同意」とみなされないケースもあるため注意が必要です。また、配信したメールには必ずオプトアウト(配信停止)の方法を明記する義務があります。
「解除リンク」「連絡先メールアドレス」など、受信者が容易に配信停止できる仕組みを用意しておかなければ違反となりかねません。自社が誤って法律違反をしてしまうと、罰則だけでなく信頼低下にもつながります。
スパム対策は“受信”だけでなく、「送信側の健全性」も維持することが重要です。
まとめ

スパムメールとの戦いは、日々新たな手口が生まれる「いたちごっこ」です。特に中小企業はリソースが限られているため、一つのメールが深刻な経営リスクへと直結しかねません。だからこそ、攻撃を「自分ごと」として捉え、段階的に対策を進めていくことが重要です。
本記事で紹介したポイントは次の3点です。
1. 従業員の意識(見分け方)を高めること
送信元アドレスやURLの確認など、日常的にできるチェックは多く、教育と訓練によってリスク低減が可能です。
2. 巧妙な攻撃は「個人の注意」だけでは防げないと認識すること
標的型攻撃やBECのように、本物と見分けがつかないメールは誰でも誤って開封してしまいます。ミス前提で仕組みを整えることが経営者の役目です。
3. 中小企業こそ、管理が容易で効果の高い「クラウド型メールセキュリティ」を導入すべきこと
ゲートウェイ(入口)で脅威をブロックできれば、従業員の端末まで危険なメールが届く確率を大幅に下げられます。専任担当者が不要で最新の脅威に自動対応できるクラウド型は、中小企業に最適かつ現実的な選択肢です。
日々変化する脅威に備えながら、会社と従業員、そして取引先を守る体制を整えていきましょう。必要な対策を一つずつ実行することが、長期的な信頼と事業継続につながります。
使えるねっとは、これまで多くの中小企業のIT環境を支えてきたクラウド・ホスティングの専門企業です。メールセキュリティの強化は、もはや「一部の大企業だけの課題」ではありません。限られたリソースで事業を運営する中小企業こそ、確実に効果があり、運用負担の少ない仕組みを選ぶことが重要です。
「使えるメールバスター」は、スパムメール・ウイルス・標的型攻撃を入口でブロックし、従業員の端末に危険なメールを届かせないためのクラウド型ゲートウェイサービスです。導入も簡単で、専任の担当者がいなくても運用できます。
FAQ

スパムメール対策は、従業員の注意だけでは不十分なのでしょうか?
不十分です。従業員の教育は重要ですが、標的型攻撃やBECのように、本物そっくりの文面で巧妙に偽装されたメールは「注意力だけで見抜く」ことが困難です。そのため、中小企業は“ミスが起きても被害が出ない仕組み”として、ゲートウェイ(入口)で脅威を遮断できるクラウド型メールセキュリティの導入が不可欠です。
スパムメール対策として、PCのウイルス対策ソフトだけではダメですか?
ウイルス対策ソフトは大切ですが、あくまで「最後の砦」です。危険なメールが端末に届いてからの対策では、感染や情報漏えいを完全に防げません。理想は、PCに届く前、メールサーバの手前でスパム・ウイルスを自動で検知・隔離するゲートウェイ対策(使えるメールバスターなど)を併用することです。
中小企業でも送信側の対策(SPF・DKIM・DMARC)は必要ですか?
はい、必要です。SPF・DKIM・DMARCは「なりすまし防止」のための基本設定であり、自社が加害者にならないための必須対策です。特に自社ドメインが悪用されると、顧客や取引先からの信用を失い、メール配信がブロックされる可能性もあります。使えるねっとのホスティングサービスであれば、これらの設定にも対応しており、専門知識がなくても安全に導入できます。
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)