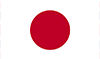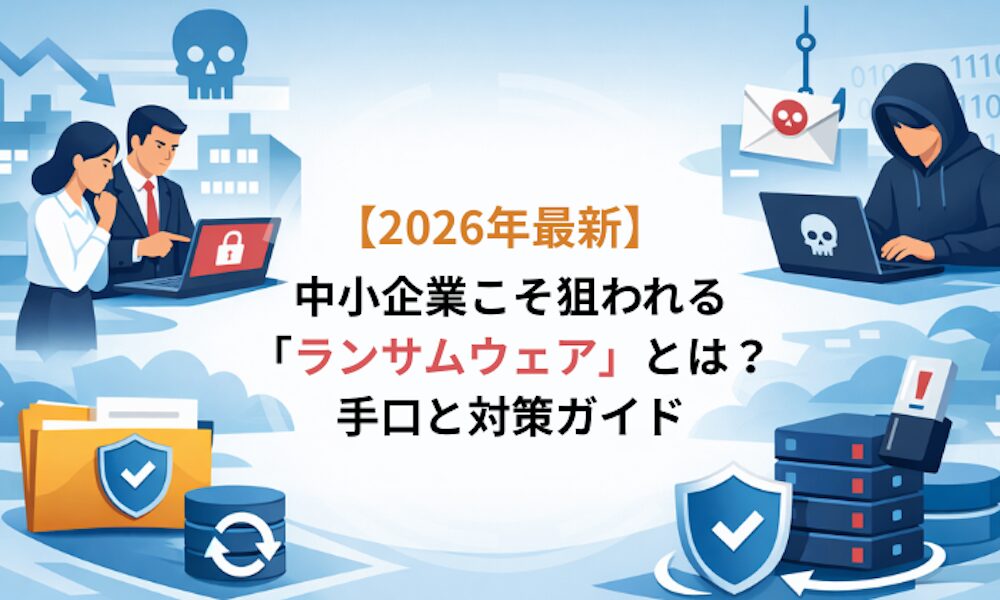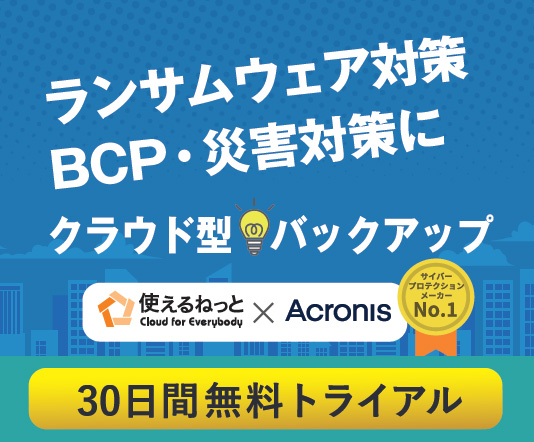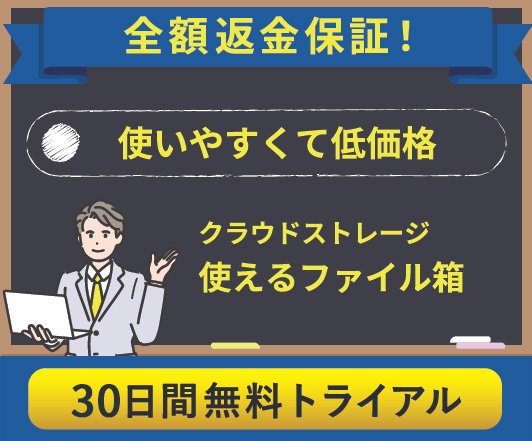迷惑メールやウイルスメールの対策として、多くの企業が導入している「メールセキュリティ」。特に中小企業にとっては、オンプレ型とクラウド型サービスのどちらを選ぶべきか悩ましいところです。
本記事では、両者の違いやそれぞれのメリット・デメリット、具体的な製品比較までを解説します。クラウド導入を検討している企業様に向けて、導入のヒントもお届けします。
目次
メールセキュリティとは?企業にとっての重要性
オンプレ型メールセキュリティの特徴と課題とは?
クラウド型メールセキュリティの特徴とは?
クラウドとオンプレの比較|中小企業が導入を検討すべきポイント
使えるメールバスターと他社サービス
導入前に押さえておきたいチェックポイント
FAQ
メールセキュリティとは?企業にとっての重要性

メールがサイバー攻撃の主要な入口である理由
メールは、企業の業務に不可欠なインフラであり、顧客・取引先・社内メンバーとのやり取りの中心を担っています。しかし、逆にこの利便性こそが攻撃者にとって絶好の狙い目にもなり得ます。
特にフィッシング詐欺、マルウェア感染、ビジネスメール詐欺(BEC)といった手口は、年々巧妙化・多様化しています。取引先のドメイン名に似せたアドレスから請求書を装ったメールを送り、従業員が誤って開封・送金してしまう事例も後を絶ちません。攻撃者にとってメールは「正規のコミュニケーションを装いやすい」媒体であり、企業側のセキュリティ網をすり抜けやすいという特徴があります。
さらに、受信者が日常的に目を通すものなので、不審メールに気づかず開封してしまう確率が高く、人間の判断ミスを突く「ソーシャルエンジニアリング攻撃」と非常に相性が良いのです。
「迷惑メールブロック」「スパムネット」「脆弱性」「EDR」など関連用語の解説
| 関連用語 | 意味・内容 |
| 迷惑メールブロック | 広告メールや詐欺メールなど、業務に不要なメールを自動的に検出・隔離し、受信トレイをクリーンな状態に保つ機能。スパムフィルタとも呼ばれます。誤検知や「すり抜け」を防ぐため、定期的なルール更新やAIによる判定精度の向上が行われます。 |
| スパムネット | 世界中に分散した感染PCや不正サーバを経由してスパムメールを大量送信するネットワークのこと。攻撃者はこれを使って短時間に数百万通ものメールをばらまき、特定の企業を狙い撃ちします。 |
| 脆弱性 | ソフトウェアやシステムの設計上の欠陥で、攻撃者が侵入や悪用に利用できる部分。脆弱性が放置されると、添付ファイルやリンク経由で簡単に侵入される危険があります。 |
| EDR (Endpoint Detection and Response) | 端末(パソコンやスマートフォン)レベルで不審な挙動を検知・解析し、迅速に対応するセキュリティ技術。メールセキュリティと併用することで、メールから侵入したマルウェアの二次被害を防止します。 |
メールセキュリティがなければどうなるのか
メールセキュリティを導入していない場合、以下のような深刻な被害が発生する可能性があります。
・ランサムウェア感染
従業員が添付ファイルを何の疑いもなく開封し、社内サーバやPCが暗号化されて業務が完全停止。復旧には多額の費用と時間がかかります。
・偽請求書による送金被害
巧妙に作られた偽の請求書メールを受け取り、経理担当者が誤って送金。数百万円規模の損害が出るケースも珍しくありません。
・顧客情報の流出
メール経由で社内の顧客リストや契約情報が外部に漏えいすることによる、取引先からの信用問題。信用失墜は新規受注の減少や契約打ち切りにつながります。
特に中小企業では、専任のセキュリティ担当者や24時間の監視体制が整っていないことが多く、ひとたび被害に遭えば事業継続に直結する危機になります。実際に、中小企業の情報漏えい事故の多くがメール経由で発生しており、しかもその多くは基本的なセキュリティ対策で防げた事案です。
オンプレ型メールセキュリティの特徴と課題とは?
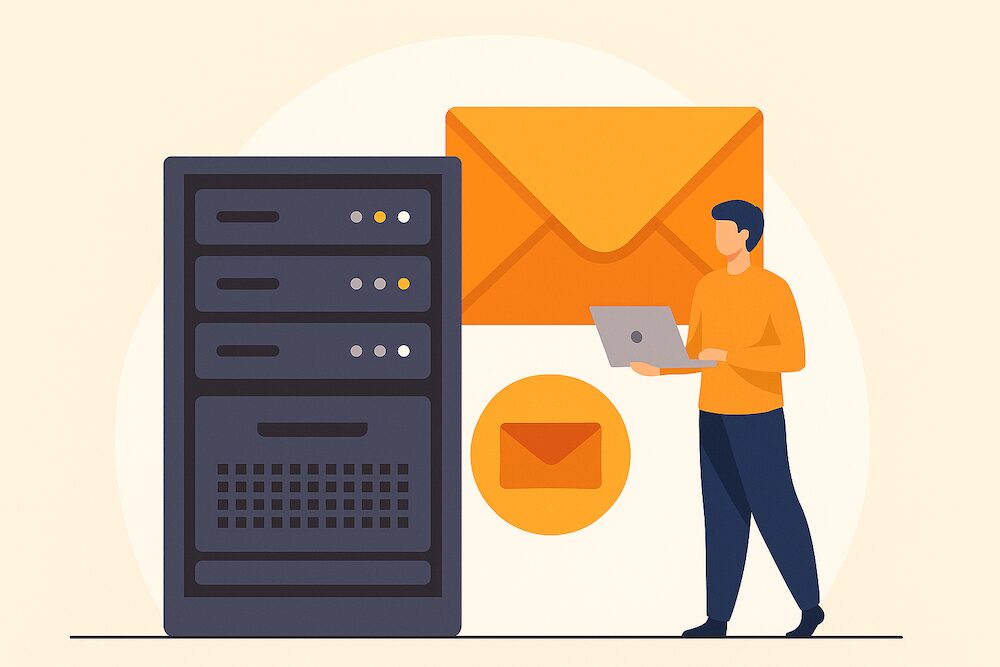
オンプレ型とは何か?
オンプレ型(オンプレミス)とは、サーバやネットワーク機器、セキュリティ機器などを自社の施設内に物理的に設置し、自社で運用・管理する形態のことです。メールセキュリティをオンプレで構築する場合は、自社内に設置したメールサーバや専用アプライアンスを経由して、送受信メールの検査・フィルタリングを行います。
この形態では、ネットワーク構成やセキュリティポリシーを細かく設定でき、外部依存を最小化できるのが特徴です。例えば、特定の部署だけに適用するルールや独自のウイルス定義更新スケジュールを組み込むなど、きめ細かな運用が可能です。
導入にはファイルサーバやSSL証明書、ファイアウォール等が必要
オンプレ型のメールセキュリティ導入には、以下のような環境構築が必要です。
| ファイルサーバ | メールの添付ファイルやログデータの保管、隔離ファイルの保存先として使用します。 |
| SSL証明書 | メール通信の暗号化に必須。証明書の有効期限管理や更新手続きも必要です。 |
| ファイアウォール | 外部からの不正アクセスを防ぎ、内部ネットワークを保護します。メールポートの設定やアクセス制御ルールの管理も欠かせません。 |
これらの設備は、単に導入するだけでなく正しい設定と定期的な保守が不可欠です。設定不備や更新漏れは、攻撃者に侵入経路を与えてしまう「セキュリティホール」となります。
管理コスト・サーバ運用・定期的な更新など中小企業における実情
オンプレミス型のメールセキュリティは、自社環境を細かく制御できる反面、運用・保守にかかるコストと人的負担が大きいのが現実です。中小企業の場合、その影響は特に顕著です。
まず、管理コストの面では、サーバやネットワーク機器の購入費用だけでなく、設置工事、ラックや空調などの設備投資、そして年間保守契約費が必要です。導入時の初期費用が高額になるうえ、保守契約やライセンス更新料などの固定費が毎年発生します。
サーバ運用では、日常的な稼働監視、障害対応、ログ管理、アクセス権限の設定など、継続的な作業が欠かせません。特にメールシステムは24時間稼働が前提のため、夜間や休日のトラブルにも即応できる体制が求められます。専任のIT担当者がいない企業では、他業務と兼務しながら対応せざるを得ず、負担が集中します。
また、定期的な更新作業も避けられません。OSやセキュリティソフトのアップデート、ウイルス定義ファイルの更新、SSL証明書の更新、ハードウェアの部品交換などが必要で、これらを怠ればセキュリティホールが生じ、外部からの攻撃にさらされる危険が高まります。さらに、機器の老朽化に伴うリプレースでは、再度多額の投資が必要です。
総じて、オンプレミス型は導入して終わりではなく、運用を継続するための時間・人材・予算を長期的に確保できるかどうかが成功の分かれ目です。中小企業ではこうしたリソースを十分に割けないケースが多く、結果としてクラウド型への移行を検討するきっかけとなることも少なくありません。
クラウド型メールセキュリティの特徴とは?

インターネット経由で提供されるセキュリティサービスの仕組み
クラウド型メールセキュリティは、自社に物理的なサーバや専用機器を設置せず、インターネット経由で提供されるセキュリティサービスを利用して、メールの安全を確保します。
送受信されるメールは、まずサービス提供者のクラウド環境を通過し、ウイルス・スパム・フィッシングなどの脅威を検出・隔離したうえで、クリーンな状態で社内のメールサーバや端末に届けられます。最新の脅威情報や検知エンジンが自動更新されるため、常に最新のセキュリティ状態を維持できるのが大きな特徴です。
バックアップ・ストレージと同様、段階的に導入しやすい
クラウド型は、物理機器の購入や大規模なネットワーク構築が不要なため、初期費用を抑えつつ導入できます。利用規模に応じてライセンス数や機能を段階的に拡張でき、急な人員増加や拠点追加にも柔軟に対応可能です。これは、クラウドバックアップやオンラインストレージと同様のスケーラビリティを持っており、まずは最小構成から試すことができて、リスクの少ない導入が可能です。
マネージドサービスのメリット:「使えるメールバスター」の活用例
クラウド型メールセキュリティの中でも、「使えるメールバスター」は中小企業に適したマネージドサービスです。ウイルス・スパム検出率99.98%という高精度のフィルタリング機能を備え、迷惑メールや不正添付ファイルを自動的に隔離・削除します。導入時の設定もシンプルで、専門知識がなくても短時間で稼働開始が可能。さらに、セキュリティ定義ファイルの更新や障害対応はすべてサービス側で行われるため、自社内の運用負担を大幅に軽減できます。
「クラウドサーバ」「クラウドバックアップ」との連携
クラウド型メールセキュリティは、他のクラウドサービスと連携することで、より強固なセキュリティ体制を構築できます。例えば、メール添付ファイルを自動的にクラウドストレージへ保存し、同時にクラウドバックアップで世代管理を行えば、万が一のデータ破損やランサムウェア感染時にも迅速な復旧が可能です。これにより、メールセキュリティだけでなく、データ保護や事業継続計画(BCP)の強化にもつながります。
クラウドとオンプレの比較|中小企業が導入を検討すべきポイント

| 比較項目 | オンプレ型(オンプレミス) | クラウド型 |
| 初期費用 | 高い(サーバ機器、ネットワーク機器、構築費用が必要) | 低コスト(機器不要で契約後すぐ利用可能) |
| 管理者負担 | 自社IT担当者が運用・保守を継続して実施 | ベンダーが監視・保守を行い、自社負担を軽減 |
| 拡張性 | 利用者増加や機能追加時に機器の増設・設定変更が必要 | 契約プラン変更だけで利用量や機能をスケーラブルに拡張可能 |
| 専門知識 | サーバ・ネットワーク・セキュリティの専門知識が必須 | 基本的な操作知識で運用でき、高度設定はベンダーに依頼可能 |
| 障害時対応 | 自社で原因特定・復旧を実施、夜間・休日対応も必要 | クラウド側で障害対応・復旧を行い、利用者への影響を最小化 |
中小企業のリソースを考慮した選定基準
中小企業では、専任のIT担当者が不在、またはごく少人数での運用体制が一般的です。そのため、ITシステムの保守や運用に割ける時間・人材・予算が限られています。
オンプレ型のメールセキュリティは、自社でサーバやネットワーク機器を運用・管理する必要があり、障害対応やソフトウェア更新などに多くの工数と人件費がかかります。特に夜間や休日のトラブル対応までカバーするには、相応の体制整備が必要です。
一方、クラウド型メールセキュリティは、機器の設置や複雑なネットワーク構築が不要で、管理業務の多くをサービス提供側が担います。「管理の自動化」や「直感的に操作できるUI」によって、ITの専門知識が乏しい環境でもスムーズに運用でき、担当者の負担を大幅に軽減できます。結果として、セキュリティ品質を維持しながら、社内リソースを本来の業務に集中させられるのが大きな強みです。
中小企業におすすめの判断フロー
導入形態を選ぶ際には、次の3つのポイントを順に確認すると判断しやすくなります。
1. 初期投資が可能かどうか
オンプレ型は機器購入や構築費用が高額になりがちです。初期投資の予算が限られている場合、クラウド型のほうがスムーズに導入できます。
2. 社内に管理人材がいるかどうか
専任のIT管理者が不在、または兼任体制の場合、障害対応やセキュリティ更新の負担が少ないクラウド型が適しています。
3. 今後の成長性(拠点・人員増加)を考慮する
将来的に拠点や従業員が増える見込みがある場合は、利用規模に応じて柔軟に拡張できるクラウド型が有利です。オンプレ型では機器増設や設定変更が必要になり、追加コストと工期が発生します。
このように、自社の人員体制・予算・将来計画を踏まえて選択することで、長期的に安定したセキュリティ運用が可能になります。
使えるメールバスターと他社サービス

「使えるメールバスター」の概要と強み
「使えるメールバスター」は、ビジネスにおいて常に脅威にさらされるメールからの情報資産保護を目的としたクラウド型メールセキュリティサービスです。巧妙化するスパム、標的型攻撃、情報漏えいといった多様な脅威に対し、メールがメールサーバに到達する前にブロックすることで、組織のセキュリティを強化します。
使えるメールバスターの主な強みは以下の通りです。
| 高い検出精度 | 独自の学習型AI技術を搭載しており、迷惑メールの撃退率は驚異の99.98%を誇ります。このAIは新たなスパムやウイルスにも即座に対応し、使うほどに判別精度が向上します。 |
| 簡単な導入と運用 | 完全クラウド型のためソフトウェアのインストールは不要です。MXレコードの変更というわずか3ステップ、5分程度の簡単な設定でサービスを開始でき、専門知識がない担当者でも安心して導入・運用が可能です。これにより、メールサーバの負荷を最大80%軽減し、運用コストも大幅に削減します。 |
| 多岐にわたる セキュリティ機能 | ウイルスフィルタ、迷惑メールフィルタ、IPアドレスフィルタ、添付ファイルの制限、アドレスフィルタ、DMARCチェックフィルタ、送信ドメイン認証フィルタ(SPF/DKIM)、迷惑メール送信防止機能など、受信・送信双方のセキュリティを強化します。ウェブ管理システム画面から一括管理が可能です。 |
これらの特徴から、使えるメールバスターは、初期コストを抑えつつ迅速にメールセキュリティ対策を強化したい中小企業やスタートアップに最適なソリューションとして位置づけられます。
小規模企業・スタートアップに最適な構成例
小規模企業やスタートアップは、ITリソースが限られる中で包括的なセキュリティ体制を構築する必要があります。このような企業には、クラウド型の使えるメールバスターが特に適しています。さらに、同じ使えるねっとが提供する他のクラウドサービスを組み合わせることで、メールセキュリティを超えた包括的な情報資産保護のエコシステムを構築できます。
例えば、使えるメールバスターでメールの脅威を入口で防ぎつつ、以下のサービスを組み合わせることで、データ保存やバックアップまでカバー可能です。
| 使えるファイル箱 | ユーザー数無制限のクラウドストレージとして、ファイル共有の安全性を高めます。 |
| 使えるクラウドバックアップ | ランサムウェアや災害対策に有効なクラウド型バックアップサービスで、AIベースのアクティブプロテクション技術によりマルウェア対策も強化します。また、災害やサイバー攻撃からの復旧を最短で可能にし、事業継続性を確保します。 |
これらのサービスは、限られたITリソースで最大限のセキュリティ効果を得るために役立ちます。
中小企業に特に適した選択肢は?
中小企業がメールセキュリティソフトを選ぶ際には、自社のITリソース、直面する脅威の種類、重視する機能に応じて最適な選択肢を検討することが重要です。
まず、使えるメールバスターは初期費用が無料で手頃な月額料金が特徴。ドメイン単位で分かりやすい料金設定で、1ドメインで300メールアカウントの登録が可能です。1年契約プランなら、月単価11,770円、1アカウントあたり39円〜。
また、URLフィルタリング、シャドーIT対策、アンチウイルス、サンドボックスオプションに加え、誤送信防止に特化した機能を提供します。国内企業、教育機関、自治体での導入実績が豊富で、細かなポリシー管理が必要な場合に適しています。送信一時保留機能や上長承認フロー、宛先BCC強制変換などの機能も、誤送信対策として有効です。
さらに、トレンドマイクロの統合セキュリティプラットフォーム「Trend Vision One」と連携し、XDRやEDRとの連携も可能であるため、ゼロトラスト戦略を推進したい企業や、より広範な攻撃対象領域の脅威検出と迅速なインシデント対応を求める企業に適しています。
Emotetのようなマルウェアはメールを介して感染が拡大した事例があり、添付ファイル型攻撃への対策は不可欠です。これには、サンドボックス機能(疑わしいファイルを仮想環境で実行して安全性を検証)、添付ファイル無害化、リアルタイムスキャンなどの機能が有効です。多くのメールセキュリティソフトがこれらの機能を提供しており、「使えるメールバスター」もスパム、フィッシング、ウイルス、ランサムウェア等のマルウェア対策を講じています。AIによる振る舞い検知エンジンも、未知のマルウェアを含む不審なメールを高精度でブロックするのに役立ちます。
導入前に押さえておきたいチェックポイント

セキュリティポリシーの明確化
メールセキュリティを導入する前に、まず自社のセキュリティポリシーを明確化することが重要です。「どの範囲のメールを検査対象とするのか」「隔離されたメールは誰が、どのタイミングで確認するのか」など、ルールを事前に決めておくことで、運用の混乱を防げます。また、従業員への周知・教育も欠かせません。どれだけ優れたシステムを導入しても、運用ルールが徹底されなければ効果は半減します。
クラウド導入に不安がある場合は段階的導入も可
「完全クラウド化に抵抗がある」「既存システムを急に切り替えるのは不安」という場合には、オンプレ型とクラウド型を併用するハイブリッド構成も有効です。例えば、外部とのやり取りはクラウド型でフィルタリングし、社内メールはオンプレ型で運用するなど、リスクと安心感のバランスを取りながら移行できます。段階的にクラウド環境へ移行することで、運用面やコスト面での検証も行いやすくなります。
導入時には、メールルーティングや認証に関する設定変更が必要になる場合があります。具体的には、「hostsファイル」の編集や「サーバ証明書」の更新・適用などです。これらの作業はIT部門またはベンダーと連携し、事前に影響範囲を確認して進めることが重要です。準備を怠ると、導入直後にメール送受信が停止するなどのトラブルにつながる恐れがあります。
これらのポイントを事前に押さえておけば、スムーズかつ安全にメールセキュリティの運用を開始でき、長期的な安定運用にもつながります。
FAQ

クラウド型のメールセキュリティは自社のメールサーバとも連携できますか?
はい、POP/IMAP、SMTP経由で問題なく連携可能です。既存のメールサーバをそのまま利用しながら、セキュリティ機能だけを強化できます。
リモートワークでも使えますか?
はい。クラウド型は場所やネットワーク環境に依存しないため、在宅勤務や出張先など、どこからでも安全に利用できます。VPNや専用回線が不要なケースも多く、導入・運用がスムーズです。
セキュリティの更新はどうなっていますか?
クラウド型は常に最新の定義ファイルに自動更新されます。利用者側での手動更新作業は不要で、導入後も最新の脅威情報に基づいた防御が継続的に提供されます。
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)