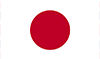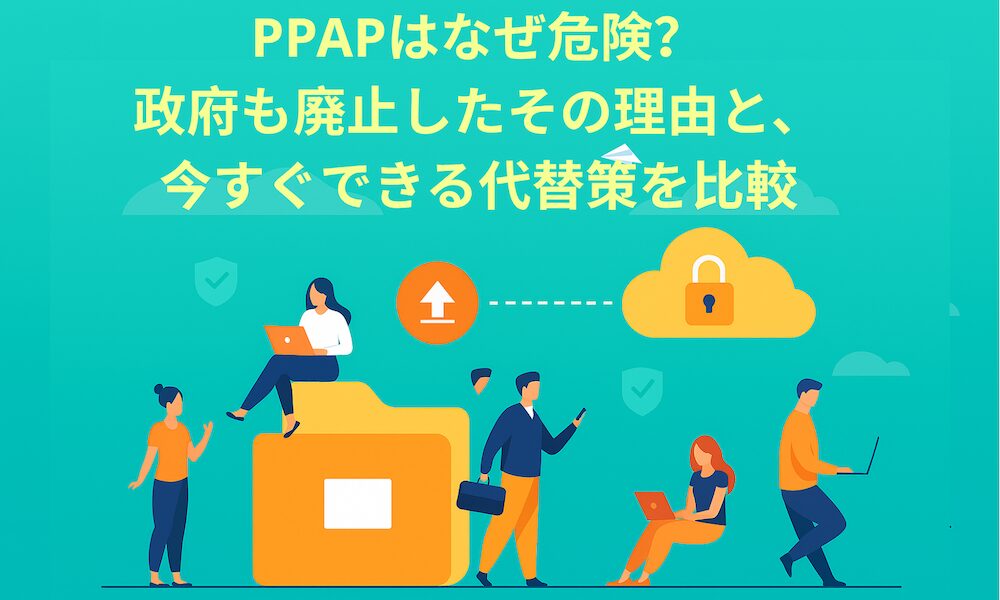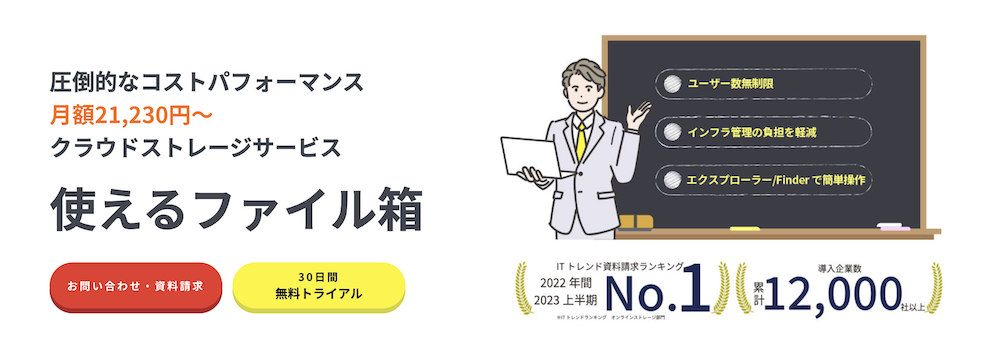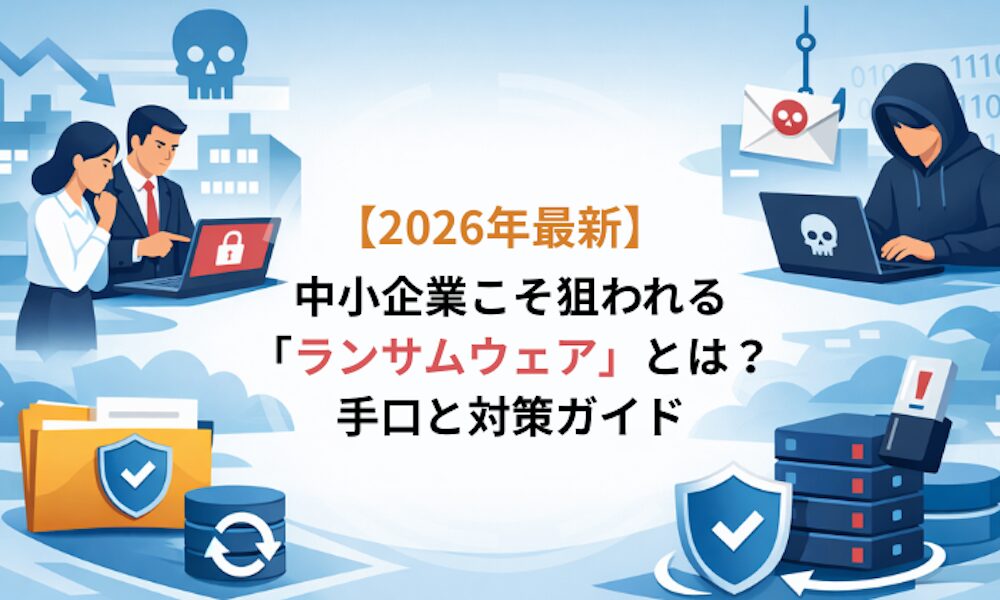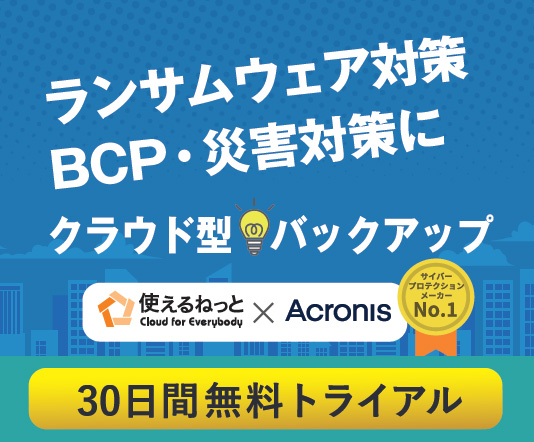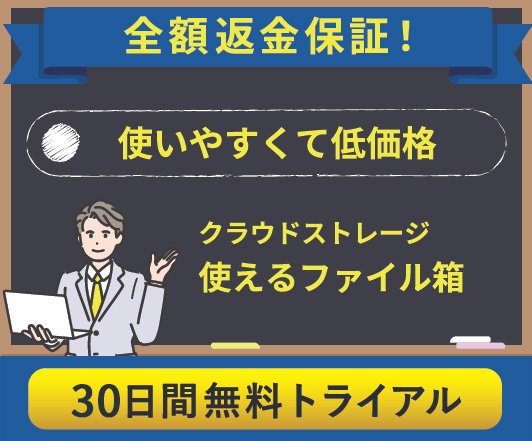「PPAP、そろそろやめたいけれど、何から始めればいいかわからない」―そんな悩みを抱える中小企業の担当者は少なくありません。ZIP暗号化とパスワード別送によるPPAP方式は、一見安全そうに思えますが、実はセキュリティ上の重大な欠陥があります。さらに、政府も2020年以降廃止を表明し、社会全体で代替策への移行が進んでいます。
本記事では、PPAPの基本と問題点を整理した上で、中小企業でも導入しやすい7つの代替策を比較。結論として、操作が簡単でサポートが手厚い国産クラウドストレージが有力な選択肢であることをご紹介します。
目次
そもそもPPAPとは?今さら聞けない基本と問題点
政府も「PPAP廃止」を宣言 - 社会全体の流れ
PPAPの代替案となる7つの主要な方法
【比較表】自社に合うのはどれ?代替案7つのメリット・デメリット
中小企業がPPAP代替案を選ぶための3つの重要ポイント
結論:中小企業のPPAP代替には「使えるファイル箱」がおすすめな理由
FAQ
まとめ
そもそもPPAPとは?今さら聞けない基本と問題点

PPAPとは、Password付きZIPファイルをメールに添付し、後からPasswordを別メールで送るというファイル送信手法の略称です。
・P: Password付きZIPファイルを送る
・P: Passwordを送る
・A: 暗号化(Encryption)
・P: Protocol(手順)
2000年代後半、情報漏えい対策の一環として官公庁や企業で広く採用されました。当時は大容量ファイル送信やクラウド活用が一般的でなかったため、「メールで送れて簡単」「暗号化できて安全」という認識が浸透していました。しかし近年、通信経路やウイルス対策の技術変化により、その安全性は大きく揺らいでいます。
なぜPPAPは危険なのか?4つの深刻なリスク
なぜPPAPは危険なのでしょうか?以下では4つの具体的なリスクについて説明します。
リスク1:経路上での盗聴(同一経路問題)
PPAPでは、ZIPファイルとパスワードをそれぞれ別のメールで送りますが、どちらも同じメール経路を通過します。そのため、もし通信経路上で盗聴やメールサーバへの不正アクセスが行われた場合、両方を傍受されてしまう可能性があります。結果として、暗号化の意味が失われ、ファイルの中身が簡単に解読されてしまうのです。
リスク2:ウイルスチェックの無効化
暗号化ZIPファイルは、その中身をセキュリティソフトが検査できません。この仕組みを逆手に取り、マルウェア(特にEmotetなど)を仕込んだファイルが拡散される事例が後を絶ちません。受信者が不用意にファイルを解凍してしまうと、端末や社内ネットワーク全体に感染が広がる危険性があります。
リスク3:パスワードの脆弱性
「1234」「password」といった単純すぎるパスワードや、過去に使ったパスワードを使い回すことは、総当たり攻撃や漏えいデータベースを利用した不正アクセスに対して極めて脆弱です。仮に別送しても、パスワードの強度が低ければ安全性はほぼ確保できません。
リスク4:業務効率の低下
PPAPの運用には、送信者・受信者双方に手間がかかります。ファイルのZIP化、パスワードの設定、別メールでの送信、受信側での解凍―こうした作業は一つひとつは小さくても積み重なれば大きな時間のロスとなります。その結果、本来の業務に割ける時間が減り、生産性低下を招きます。
政府も「PPAP廃止」を宣言 - 社会全体の流れ

近年、情報セキュリティ対策として広く用いられてきた「PPAP」に終止符が打たれようとしています。この動きは単なる民間企業の流行ではなく、政府自らが率先して廃止を宣言し、社会全体でのセキュリティ向上を促す方針であることを示しています。
内閣府の平井卓也特命担当大臣(当時)は、2020年11月24日の記者会見において、内閣府と内閣官房での自動暗号化ZIPファイルの廃止を発表しました。この廃止は、利用者目線でのデジタル改革推進の象徴といえます。
会見では、ZIPファイルとパスワードを同じ経路で自動送付する方式は「セキュリティ対策の観点からも、受け取る側の利便性の観点からも、適切なものではない」、「全く別の経路でパスワードを知らせる」ことが適切であるとの認識が強調されました。
さらに重要な点は、この取り組みが内閣府と内閣官房に留まらないことです。政府はNCO(国家サイバー統括室、旧内閣サイバーセキュリティセンター)と連携して他省庁の実態調査を進めており、その結果を踏まえ、同様のPPAP方式を廃止する動きは中央省庁だけでなく、地方自治体にも広がっています。
また、この動きは「政府内だけでなく、民間にも影響のあるもの」と位置づけられており、民間企業の対応も注視しつつ、社会全体のセキュリティ向上策を模索していく姿勢が示されています。政府は、民間企業からの知恵やアイデアの投稿も歓迎すると呼びかけました。
このように、政府が明確な方針を示し、率先してPPAP廃止に踏み切ったことは、この対策が一時的なトレンドではなく、「国民の利便性を実現していく上で重要な政府方針」であることを強く示唆しています。
企業や組織は、この政府の動きを単なる業務効率化の一環と捉えるだけでなく、セキュリティ対策の根幹に関わる国家的な方向性として受け止め、早急な対策を講じる必要に迫られているといえるでしょう。
PPAPの代替案となる7つの主要な方法

PPAP廃止に伴い、企業は安全かつ効率的なファイル共有手段への切り替えを迫られています。ここでは、代表的な7つの代替方法を紹介します。
1. クラウドストレージ(Google Drive, OneDrive, 使えるファイル箱など)
オンライン上にファイルを保存し、URLリンクで共有する方式です。アクセス権限の細かい設定や共有履歴の管理が可能で、容量制限も自社のニーズに合わせて自由に変えることができます。セキュリティと利便性の両立が可能ですが、サービス選定や初期設定が必要になる場合があります。
2. ファイル転送サービス(ギガファイル便など)
一時的にファイルをアップロードし、期限付きのダウンロードリンクを送ります。アカウント登録が不要で手軽に使える反面、無料版では暗号化やサポート体制が不十分な場合があります。
3. メール暗号化(S/MIME)
メール本文や添付ファイルを暗号化する仕組みです。普段使っているメールソフトから直接利用できるメリットがありますが、証明書の取得や設定が複雑で、IT知識が必要です。
4. ビジネスチャットツール(Slack, Teamsなど)
チャット内で安全にファイルを共有でき、コミュニケーションと一体化できます。ただし、取引先も同じツールを導入している必要があります。
5. セキュアコンテナ
端末上に仮想的な環境を構築し、専用アプリ内でのみ開けるファイル形式を利用します。アクセス制御が高度で不正利用を防げますが、相手側にもアプリ導入を求めるため、利用ハードルは高めです。
6. EDR(Endpoint Detection and Response)
端末レベルで脅威を検知・防御する高度なセキュリティ対策です。防御力は非常に高いですが、導入・運用コストが大きく、専門人材が必要です。
7. Webダウンロード
社内のWebサーバやポータルサイトにファイルを置き、取引先がそこから取得します。社内管理はしやすいものの、サーバ構築や保守が不可欠です。
以上のように、それぞれの方法は、セキュリティ強度・コスト・操作性などに特徴があります。中小企業では、使いやすさと安全性のバランスを重視し、自社の業務フローや取引先の環境に適した方法を選ぶことが重要です。
【比較表】自社に合うのはどれ?代替案7つのメリット・デメリット

以下では、7つの代替案それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。
各代替策のメリット・デメリットを表にまとめると以下のようになります。
| セキュリティ強度 | 導入コスト | 手軽さ(受信側) | 取引先への 共有しやすさ | |
| クラウド ストレージ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| ファイル 転送サービス | △ | ◎ | ◎ | 〇 |
| メール 暗号化 | 〇 | △ | △ | △ |
| ビジネス チャット | 〇 | 〇 | △ | △ |
| セキュア コンテナ | ◎ | △ | × | △ |
| EDR | ◎ | × | 〇 | △ |
| Web ダウンロード | 〇 | △ | △ | △ |
1. クラウドストレージ(Google Drive, OneDrive, 使えるファイル箱など)
メリット
・高度なアクセス権限管理:閲覧のみ/編集可/ダウンロード不可など細かく設定できる。
・履歴管理とログ監査:誰がいつアクセス・変更したかが記録され、不正利用の抑止になる。
・大容量対応:数GB〜TB単位のファイルも共有可能。
・外出先からの利用:PC・スマホ・タブレットからアクセスでき、テレワークに最適。
・バックアップ性:ローカル障害や端末紛失時でもクラウド上から復元可能。
デメリット
・サービス選定の難しさ:セキュリティ機能や価格プランが多様で、比較検討に時間がかかる。
・初期設定の手間:ユーザー登録や権限設定など導入時に一定の作業が必要。
・取引先の制約:相手が特定クラウドの利用を禁止している場合は使えない。
2. ファイル転送サービス(ギガファイル便など)
メリット
・即時利用可能:会員登録不要でアップロード〜リンク共有まで数分で完了。
・送信容量が大きい:無料でも数GB〜100GBの送信に対応するサービスが多い。
・有効期限設定:一定期間でリンクが無効化され、長期的な漏えいリスクを減らせる。
デメリット
・無料版のセキュリティ不安:暗号化やアクセス制御が弱く、運営会社のポリシーも不透明な場合がある。
・広告表示:受信ページに広告が表示され、ビジネス上の印象を損ねることがある。
・サポート体制の欠如:障害時や誤送信対応などのサポートが基本的にない。
3. メール暗号化(S/MIME)
メリット
・メール本文も保護可能:添付ファイルだけでなく本文も暗号化できるため機密性が高い。
・既存環境と連携:普段のメールソフトで利用でき、追加ツールが不要。
・送信相手を限定可能:証明書を発行した相手のみと安全に通信できる。
デメリット
・導入・設定の難易度:証明書の取得、インストール、設定が必要でITスキルが求められる。
・相手側の対応必須:受信側もS/MIMEに対応していないと利用できない。
・費用負担:有効な証明書を継続利用するための費用が発生する。
4. ビジネスチャットツール(Slack, Teamsなど)
メリット
・会話とファイル共有の一元化:議論の流れと添付資料を同じ場所で管理できる。
・検索性の高さ:過去のファイルやメッセージを高速検索可能。
・権限管理:チャンネル単位で共有範囲を制御できる。
デメリット
・取引先導入の壁:相手企業も同じツールを導入しないと共有できない。
・情報の分散:メールや別クラウドと併用すると情報が散らばる可能性がある。
・外部連携のセキュリティリスク:アプリ連携機能を使う場合、権限設定に注意が必要。
5. セキュアコンテナ
メリット
・高度なセキュリティ:開封期限やコピー禁止設定、スクリーンショット防止など細かい制御が可能。
・アクセス監視:不正アクセスが試みられた場合に通知される機能を備えることが多い。
・オフライン利用制御:端末に保存しても開封条件を制御できる。
デメリット
・利用ハードルの高さ:受信者も専用アプリをインストールする必要がある。
・導入コスト:比較的高額なサービスが多く、中小企業には負担になりやすい。
・操作習熟:利用者が慣れるまで時間がかかる場合がある。
6. EDR(Endpoint Detection and Response)
メリット
・高度な脅威検知:不審な動作やファイルをリアルタイムで監視・隔離。
・ゼロデイ攻撃にも対応:未知のマルウェアに対してもふるまい検知が可能。
・集中管理:複数端末のセキュリティ状況を一括で監視・管理できる。
デメリット
・高コスト:導入・ライセンス・運用費用が高額。
・運用負担:アラート分析や対応に専門知識が必要。
・ファイル共有そのものの仕組みではない:PPAP代替の直接手段ではなく補助的。
7. Webダウンロード
メリット
・自社管理の安心感:社内ポリシーに合わせたアクセス制御やログ取得が可能。
・継続利用に強い:取引先との定期的なファイル交換に向く。
・ブランド統一:自社ドメインを利用すれば信頼性を高められる。
デメリット
・構築コスト:サーバやCMSの設計・構築が必要。
・保守負担:セキュリティパッチ適用や障害対応など継続的な管理が不可欠。
・インターネット公開リスク:設定不備で外部からアクセス可能になる危険性がある。
中小企業がPPAP代替案を選ぶための3つの重要ポイント

PPAP廃止の流れを受け、ファイル共有方法の見直しは中小企業にとって喫緊の課題となっています。しかし、選択肢が多すぎて「どれが自社に最適なのか」迷う担当者は少なくありません。ここでは、中小企業がPPAPの代替策を選定する際に重視すべき3つのポイントを整理します。
ポイント1:IT担当者不在でも運用できるか?
多くの中小企業では、専任のIT担当者がいない、もしくは兼任で運用しているケースがほとんどで、導入後の設定や日常的な管理が複雑なツールは不向きといえます。
理想は、管理画面が直感的で分かりやすく、日本語でのサポート体制が整っているサービスです。海外製のツールは機能面で優れていても、初期設定やトラブル対応の際に英語マニュアルしかない場合が多く、運用ハードルが高くなります。サポート窓口が国内にあり、電話やメールで迅速に対応してもらえる環境も必要になります。
ポイント2:取引先のITリテラシーに合わせられるか?
どれだけ安全性の高いサービスでも、取引先がファイルを簡単に受け取れなければ意味がありません。中小企業間のやり取りでは、相手のITリテラシーや社内ルールがまちまちであり、複雑なアカウント登録やアプリ導入を求めると、受信側の負担になり業務が滞ります。したがって、相手がアカウント登録不要で、リンクをクリックするだけでファイルを開けることは重要な条件です。操作が直感的であれば、初めて利用する取引先でもスムーズに受け取れ、トラブル対応に割く時間を減らせます。
ポイント3:コストとセキュリティのバランス
無料のファイル転送サービスは手軽ですが、サポートがなくセキュリティポリシーが不透明なケースも多く、業務利用には不安が残ります。一方、大企業向けの高機能セキュリティ製品は導入・運用コストが高く、中小企業にはオーバースペックです。
現実的なのは、月額数千円程度で導入でき、必要十分なセキュリティ機能とサポートを備えた中小企業向けサービスです。こうしたサービスであれば、費用負担を抑えながら安全性と利便性の両方を確保できます。
結論:中小企業のPPAP代替には「使えるファイル箱」がおすすめな理由
1. 直感的操作と純国産の安心感
「使えるファイル箱」は、普段お使いのパソコンと同じようにWindowsのエクスプローラーやMacのFinderでデータのアップロード、ダウンロード、共有が可能なため、使い慣れた操作感で利用できます。ITに詳しくない方でも、ファイルのコピー、貼り付け、ドラッグ&ドロップ、ショートカットキーなど、いつものフォルダ操作と全く同じ感覚でデータ保存や共有が行えるため、全社員に操作を教える手間やコストがかかりません。
実際に導入した中小企業の担当者様からも、その使いやすさとシンプルな操作性、そして簡易マニュアルで理解できるほどのわかりやすさが導入の決め手になったと評価されています。
また、データセンターは国内(長野)に設置されており、地震などの災害対策が整った環境で管理されているため、純国産ならではの安心感があります。使えるねっとは20年以上にわたりサービス提供に努めてきた企業であり、日本の産業を支える中小企業のニーズに合わせた「機能性、安定性、価格のバランス」を重視しています。
2. アカウント不要で受信者も簡単ダウンロード
取引先とのデータ共有は、「共有フォルダの作成」と「共有リンクの作成」の二通りで行えます。特に、頻繁なやり取りがない一時的な取引先や、メールの容量を気にせずに大容量ファイルを共有したい場合には、「共有リンク」が非常に便利です。共有リンクは、ファイルを右クリックするだけで簡単に作成でき、そのリンクをメールなどに貼り付けることで、相手側はアカウント登録などの手間なく直接データをダウンロードできます。
また、共有リンクにはパスワードや有効期限を設定できるほか、ダウンロード回数制限、宛先の指定、閲覧のみ・ダウンロードのみの設定など、高度なセキュリティ設定が可能です。万が一、誤って共有リンクを送ってしまった場合でも、リンクを無効にするだけでデータを閲覧不可にできるため、セキュリティ面でも安心です。
3. ユーザー数無制限で月額低価格
「使えるファイル箱」は、その名の通り使い勝手がよく、ユーザー数が無制限であることが大きな特長です。社員が増えても、ユーザー数に応じた課金による費用の増加や権限発行の煩わしさに悩むことがありません。価格面でも圧倒的なコストパフォーマンスを誇り、容量1TBのスタンダードプランは月額25,520円(税込、1年契約の場合)。さらに1TBあたり月額9,300円(税抜)で無制限に追加可能です。
「使えるファイル箱」は直感的な操作性、国内データセンターの安心感、アカウント登録不要の共有リンクによる利便性、そしてユーザー数無制限・低価格な料金体系により、中小企業のPPAP代替として非常に有効なソリューションです。まずは30日間の無料トライアルで使い勝手を試してみてください。
FAQ

Q. 無料のファイル転送サービスではダメですか?
A. 業務での利用には慎重になるべきです。
無料のファイル転送サービスは確かに手軽で便利ですが、ビジネス用途にはいくつかの注意点があります。まず、無料版では通信の暗号化やファイルへのアクセス制限が不十分なことがあり、取引先との機密情報のやり取りには不向きです。中小企業であっても、情報漏えいや信用リスクは致命的になり得るため、コストだけでなく「安心して使えるかどうか」を基準に選ぶことが重要です。
Q. 取引先からPPAPでファイルが送られてきた場合はどうすればよいですか?
A. 感染リスクを避けるため、社内での対応と取引先への連絡をおすすめします。
まず、添付されたZIPファイルはすぐに開封せず、必ずウイルススキャンを実施してください。暗号化されているため、一部のセキュリティソフトでは中身をチェックできない場合もありますが、解凍前に確認することが基本です。その上で、可能であれば取引先に対して、PPAP以外の安全なファイル共有方法(例:クラウドストレージ)への切り替えを依頼するとよいでしょう。
Q. PPAPの代替策を導入する前に、社内で準備しておくべきことはありますか?
A. はい、スムーズな運用のためにいくつかの社内整備が必要です。
新しいファイル共有ツールを導入する際には、まず社内の運用ルールをあらかじめ決めておくことが大切です。たとえば、「どのファイルを共有対象にするのか」「誤送信時の対応はどうするか」「アクセス権限の付け方」などを事前に定めておきましょう。さらに、社員全員が迷わず使えるように簡単な利用マニュアルを作成するのも効果的です。
まとめ

PPAP代替策の選定では、「IT担当者がいなくても使えるか」「取引先が簡単に利用できるか」「コストとセキュリティのバランスが取れているか」の3点が重要です。この条件を満たすサービスを選べば、PPAP廃止後も安全かつスムーズなファイル共有を実現できます。中小企業にとっては、国産クラウドストレージのように使いやすくサポートが手厚い選択肢が有力候補となるでしょう。
お電話でのお問い合わせはこちら:03-4590-8198
(営業時間:10:00-17:00)